脳磁図臨床応用ガイドライン(国際臨床神経生理学会推薦)
脳磁図(Magnetoencephalography, MEG)は、最先端の脳機能測定機器として高い注目を浴びていますが、これまでの研究の多くは基礎神経科学分野におけるものでした。しかし、近年、その臨床応用が世界中で急速に進み、日本においても保険適用が認められたことをきっかけに、脳神経外科、神経内科、精神科などでの臨床応用が広く行われるようになってきています。
しかし、これまでは臨床応用ガイドラインが無く、各施設独自の基準で検査が行われてきました。そのため、脳磁図研究者や技術者から、きちんとした世界基準の臨床応用ガイドラインの作成を求める声が高まってきました。この機会に、本分野では世界最大の組織である国際臨床神経生理学会(International Federation of Clinical Neurophysiology, IFCN)が主導し、世界各国の脳磁図研究の専門家が共同執筆して(Dream Team of MEGと称されています)、脳磁図臨床応用ガイドラインが作成されました。生理学研究所の柿木隆介教授も主要メンバーの一人として、ガイドラインの作成に協力しました。
このガイドラインにより、今後は世界共通の方法によって実験が行われることになり、世界中の施設での結果を比較対照することが可能となります。その効果は多大であり、脳磁図の臨床応用は、より一層活発になることが予想されます。
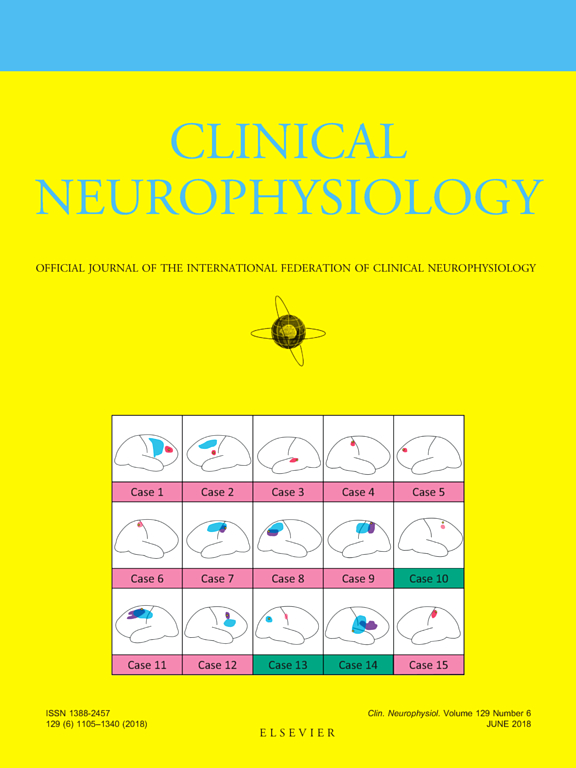
用語説明
脳磁図:神経細胞が活動する場合には、細胞内に電気信号が流れます。そして、その周囲には磁気信号が発生します。この電気信号を記録するのが、従来より行われてきた脳波であり、磁気信号を記録するのが脳磁図です。電気信号は、脳内の水分などによって大きな影響を受けますが、磁気信号は全く影響を受けないので、脳磁図は脳波に比べて格段に精密な活動記録が可能となります。また、ミリ秒単位の詳細な時間情報を得る事ができます。脳血流を測定する機能的MRI等は秒単位の時間情報しか得られないため、詳細な脳活動の時間的推移を記録するためには脳磁図が最も適切な機器です。
リリース元
Title: IFCN-endorsed practical guidelines for clinical magnetoencephalography (MEG)
Authors: Hari R, Baillet S, Barnes G, Burgess R, Forss N, Gross J, Hämäläinen M, Jensen O, Kakigi R, Mauguière F, Nakasato N, Puce A, Romani G-L, Schnitzler A, Taulu S
Journal: Clinical Neurophysiology
Issue:
Date: in press
URL (abstract): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388245718306576?via%3Dihub
DOI: https://doi.org/10.1016/j.clinph.2018.03.042

