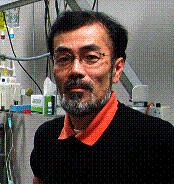|
|
(所属領域) 第ニ領域・計画班員 |
|
|
(氏名) 藤田 一郎 |
||
|
(所属・職名) 大阪大学大学院生命機能研究科 認知脳科学研究室・教授 |
||
|
(電話) 06-6850-6510
|
(FAX) 06-6857-5421
|
|
|
(E-mail) fujita@fbs.osaka-u.ac.jp |
(URL) http://www2.bpe.es.osaka-u.ac.jp/ |
|
|
(メッセージ) 私は、物体知覚、奥行き知覚に関わる神経基盤の解明を目指している。視覚行動課題遂行中の動物(主にサル)の大脳皮質視覚野細胞から活動を記録し、その性質を明らかにすることが第一ステップである。その次に進むべき道の一つは、第一ステップで見つかった特定の性質を持つ細胞が、問題としている知覚、認識、行動に本当に貢献しているのか、しているのならば、どのように関わっているのか(どのように神経情報がデコードされるのかを含む)を問う「機能追及」の方向である。もう一つの道は、そのような細胞の性質がどのような構造により実現されているのかを調べる「メカニズム追及」の方向である。本特定研究で私は、機能追求を目指した研究を遂行している。また、研究の焦点は、両眼立体視の脳内機構を明らかにすることにおいている。 研究室メンバーの数が増えると、どうしても研究テーマが拡散しそうになる。自分自身の能力からしても、時間、場所、資金のリソースの点からも無理があるし、競争力はそがれる。これは良くないことなので、研究の大筋がぶれないように意識し努力している。そうは考えているのだが、毎年受け入れている卒業研究生(学部4年)6人に研究テーマを与えるために、上記研究課題とは異なる、視覚に関わるさまざまなこと(着やせする色、バイオロジカルモーション知覚、スパイク列統計解析など)にも手を出さざるを得ない。同僚や大学院生らとともに、毎年、音を上げそうになりながら面倒を見ているのだが、やってみると、彼らはほぼ必ず、半年の卒業研究のうちにおもしろい研究の「芽」をつかんでおり(時には「果実」を収穫して、国際学会で発表したものも複数いる)、また、どのテーマも一緒にやっていてとても勉強になる。手持ちの研究時間を考えると、私の場合、ピラミッドの底辺を広げる努力よりも石を上に積み上げる時間を多くとるべきであることは明らかなのだが、彼らと学ぶ時間、彼らの成長に立ち会う大きな喜びも貴重だとも思う。 どうするべきなんだろうと考えているこのごろである。 |
||
|
(研究室で有する実験技術・リソースとその公開の可能性) a.サル、フェレット、マウスを対象とした麻酔下神経活動記録 ・
多細胞活動同時記録、単一神経細胞記録、細胞内電位記録、誘発電位記録 ・
内因性光学信号イメージング ・
イオン泳動薬物微小投与 b.行動中のサルからの単一神経細胞活動記録 c.サルを対象とした神経線維連絡解析、免疫組織化学、固定標本蛍光色素細胞内注入 d.ヒトを対象とした心理物理学的実験技術 |
||