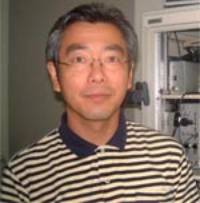|
|
(所属領域) 第2領域・公募班員 |
|
|
(氏名) 佐藤 宏道 |
||
|
(所属・職名) 大阪大学大学院医学系研究科 認知行動科学・教授 |
||
|
(電話) 06-6850-6021 |
(FAX) 06-6850-6021 |
|
|
(E-mail) sato@vision.hss.osaka-u.ac.jp |
(URL) http://www.vision.hss.osaka-u.ac.jp/ |
|
|
(メッセージ) 1982年に金沢大学医学部第2生理学教室の助手になり、津本忠治先生の研究に参加しました。ネコの一次視覚野(V1)で単純型細胞の振る舞いを初めて見たときから、「ここに大脳皮質の本質がある」と初期視覚系研究にのめりこみました。大脳皮質領野にはそれぞれの機能的・構造的特異性がありますが、その入り口にあたるV1は視床皮質投射、皮質視床フィードバック、皮質内回路、皮質間フィードバックなど、基本的な神経回路を同定しながら情報処理メカニズムを明らかにするのに好適の対象です。現在は大阪大学医学系研究科認知行動科学教室で8名の仲間と共に、麻酔下のネコおよびサルを用いて、V1と外側膝状体(LGN)のニューロン活動を定量的な視覚刺激により詳細に解析する研究を進めています。未だにヒューベルとウィーゼルのストーリーが一般的な知識となっていますが、実はLGNでもV1でも、その応答特性は刺激条件によりダイナミックに変化します。たとえばLGNニューロンには方位選択性がなく、V1に至って初めてそれが生じると信じられていますが、刺激条件によってはほとんど全てのLGNニューロンが明瞭な方位チューニングを示すようになります。初期視覚系の機能構築様式を詳細に明らかにすることは、さらにその先の高次視覚野の働きを理解する上で必須です。生物の特徴はその驚くべき経済性と合目的的性と考えていますが、特定の視覚機能がある皮質領野に至って忽然と姿を現すということはなく、視覚系の初期段階からその元になる機能が存在しています。先に行くにつれて、利用可能な情報が増えていきますから、それにより行動文脈に即した合目的的性が備わるようになると考えています。その前提となる初期視覚系の処理機能は、小さな受容野を、時空間的に定量操作できる視覚刺激を用いることで、その動的な特性を統合的に明らかにすることができます。神経生理のみならず、理論、分子生物学、形態学、心理学などを専門とする方々との共同研究で、視覚情報処理システムを統合的に解明したいと考えています。 |
||
|
(研究室で有する実験技術・リソースとその公開の可能性) (研究室で有する実験技術・リソースとその公開の可能性) ・麻酔下のネコ・サルでの視覚生理(視覚野・外側膝状体等)実験によるニューロン活動の定量的評価。 ・in
vivo microiontophoresisによる受容体作動薬・拮抗薬の効果を定量的光刺激に対するニューロン応答について調べる。 |
||