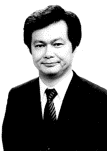|
|
(所属領域) 神経回路 |
|
|
(氏名) 桜井 正樹 |
||
|
(所属・職名)帝京大学医学部生理学講座主任教授 |
||
|
(電話)03-3964-3583(直) |
(FAX)03-5248-1415 |
|
|
(E-mail) msakurai@med.teikyo-u.ac.jp |
(URL) |
|
|
(メッセージ)私は卒業後の経歴が複雑なので、まず、はじめに若干の自己紹介を.卒業後、内科—神経内科を研修した後、伊藤正男先生の主宰される東大第一生理の大学院に入り、その後、引き続き助手をさせて頂きました.その間、伊藤先生の長年の小脳研究の一つの到達点である小脳の長期抑圧(LTD)の発見の仕事に携わることが出来ました.これに続くLTD(そしてLTP)のin vitroでの仕事は、私が心血を注いだテーマでした.伊藤先生が医学部長の大役を終えられ、ご退官になる一年前に東大神経内科に帰りましたが、3年後に金澤一郎先生が神内教授として着任されたおかげで、基礎的な研究も続けることができました.99年、東大病院の神経内科講師(外来医長・病棟医長)時代にいまのポストに招聘して頂き、現在に至っています. こちらに来てから、特に2002年以降、東大神内以来いくつかあったプロジェクトを整理し、錐体(皮質脊髄)路シナプスの形成と可塑性の問題に研究室の取り組みをほぼ一元化しました.in vitro、in vivo両標本を相互補完的に用いて研究しています.この研究の詳細については、できるだけ今夏の班会議でお話いたしたいと思います.未だ萌芽的ではありますが、面白い結果が出ています. 今回の統合脳の皆様と一緒にやっていけたらいいな、とさしあたり、思われるのは: シナプス形成における臨界期を決定する因子としてのNMDA受容体サブユニット構成の変化:NR2B→2Aの可能性(NR2B遺伝子の強制発現がin vitroで可能であれば、決定的な実験が可能では?と考えていますが---).また、NMDA受容体等の遺伝子改変動物を使えば、野生動物由来のスライスとの共培養などにより、かなり面白い実験がデザインできると思います.これまでは、錐体路についての解剖生理的データの集積が圧倒的に多いラットを使ってきましたが、遺伝子改変動物を使うことを視野にいれて、マウス(C57BL/6)での実験も開始しています. 皮質脊髄シナプス除去の運動生理的意義についても興味があり、齧歯類で前肢の運動機能評価等ができないかとも考えています. ご教示、ご指導頂ければ、また更に共同研究が一緒にできれば幸甚に存じます. |
||
|
(研究室で有する実験技術・リソースとその公開の可能性) スライス培養—分画培養(一部公開)、パッチ電極を用いたホールセル記録、フィールド記録、膜電位感受性色素を用いた光学的記録、ニューロン投射の順行性・逆行性標識、EYFP遺伝子導入によるニューロン突起の追跡—レーザー共焦点顕微鏡を用いたタイムラプス観察(これは始めたばかりで、むしろ教えを乞いたい位). |
||