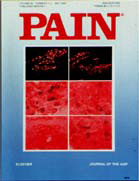|
|
(所属領域) 領域3・公募班員 |
|
|
(氏名) 野口 光一 |
||
|
(所属・職名)兵庫医科大学解剖学第二講座 ・教授 |
||
|
(電話)0798-45-6415 |
(FAX)0798-45-6417 |
|
|
(E-mail) noguchi@hyo-med.ac.jp |
(URL) |
|
|
(メッセージ) 「疼痛伝達の分子メカニズムの解明と新規疼痛治療へ向けてのシーズの開発」を教室の一貫したテーマとして,分子形態学的手法を中心に,行動薬理学,分子生物学,神経生理学手法を取り入れております。各種疼痛関連病態における神経系での各種活性物質の発現動態と、神経情報伝達の変化,感覚受容・行動の変化との関連を追求し、基本的疼痛伝達機構と各種疼痛病態の解明を進め,基礎的疼痛研究から臨床的応用へのシーズとなる結果を得ることを目的としています。 私、もともと整形外科医でありまして、当時より疼痛について興味を持っていました。20年ほど前より、疼痛が単なる症状ではなく、神経系の病気とも云える多彩な可塑的な変化に基づく病態であることがわかってきて、これは追究すべきテーマであると思い、以後研究を続けてきました。末期患者などを診ていますと、患者にとって最も必要なのは痛みを取り除くことであり、医学の原点である“不必要な痛みからの解放”を科学的に追究したいと常に思っています。「統合脳」では多くの研究者との出会いを期待しております。(写真は雑誌Painの表紙に、教室の仕事であるDRGでの遺伝子発現の変化の写真が載ったもの)。 最近の論文をご参考までに。 (1) Obata K, Katsura H, Mizushima T, Yamanaka H, Kobayashi
K, Dai Y, Fukuoka T, Tokunaga A, Tominaga M, Noguchi K,
TRPA1 induced in sensory neurons contributes to cold hyperalgesia
after inflammation and nerve injury.
J. Clin. Invest., In Press
(2) Dai Y, Wang H, Ogawa A,
Yamanaka H, Obata K, Tokunaga A and Noguchi K, Ca2+/calmodulin-dependent
protein kinase II in the spinal cord contributes to neuropathic pain in a rat
model of mononeuropathy. Eur. J.
Neurosci. 21, 2467-2474, 2005. (3) Mizushima T, Obata K, Yamanaka H, Dai,Y Fukuoka T,
Tokunaga A, Mashimo T, Noguchi K,
Activation of p38 MAPK in primary afferent neurons by noxious
stimulation and its involvement in the development of thermal
hyperalgesia, Pain, 113, 51-60,
2005 (4) Obata K, Yamanaka H, Kobayashi K, Dai Y, Mizushima T,
Katsura H, Fukuoka T, Tokunaga A, Noguchi K, Role of the MAPK activation in injured and intact primary
afferent neurons for mechanical and heat hypersensitivity after spinal nerve
ligation, J. Neurosci. 24, 10211-22, 2004
(5) Dai Y, Moriyama T, Higashi T, Togashi K, Kobayashi K, Yamanaka H, Tominaga M, Noguchi K, PAR2–mediated potentiation of TRPV1 activity reveals a mechanism for proteinase-induced inflammatory pain, J. Neurosci., 24, 4293-4299, 2004 |
||
|
(研究室で有する実験技術・リソースとその公開の可能性) 各種慢性疼痛モデルラット作成、疼痛行動測定、行動薬理、in situ ハイブリダイゼーション法、免疫組織化学法、Western blot法、ELISA等蛋白測定、基本的分子生物学的手法、パッチクランプ記録法、Caイメージング法など (基本的は手法ばかりですが、技術習得希望者受入れは可能です。 |
||