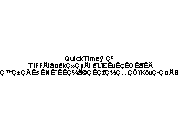|
|
(所属領域) |
|
|
(氏名) |
||
|
(所属・職名) 先端領域融合医学研究機構 |
||
|
(電話) |
(FAX) |
|
|
(E-mail) |
(URL) http:// |
|
|
(メッセージ) 私は大学院進学時より今日まで、遺伝子改変マウスの行動解析を出発点として、脳で発現する遺伝子の機能を調べてきております。22,000程度あると言われる遺伝子の半分以上は脳で発現しており、脳神経科学・精神医学研究においても、次々と作成される遺伝子改変マウスの活用により研究が加速されると考えられ、欧米では脳・行動研究においてもマウスを用いた研究の大規模化の動きがあります。日本でも、ポストゲノムシークエンスの文脈をふまえ、遺伝子改変マウスの網羅的表現型解析を起点としたラージスケールの脳神経科学・精神医学の研究を戦略的に行っていく必要があるのではないでしょうか。 「ラージスケール」といいましても、ゲノムプロジェクトと大きく異なる点は、脳神経科学における表現型解析は、多種多様で特殊な研究手法を駆使して行う必要があるということです。つまり、一カ所の「工場」だけでできるものではなく、多くの異なる分野の特殊技術を持つ研究者のコンソーシアム的な連携が必要になるでしょう。このようなラージスケールのプロジェクトは個々のスモールスケールの研究を圧迫するものでは決してなく、むしろ小さな研究室でも、大規模データベースにアクセスが可能になり様々なカッティングエッジテクノロジーやリソースを活用することができることになりますので、チャンスは大きく広がることになるのではないかと思います。これまでにたいへん高名な先生方から院生・学部生まで、多くの方々のご賛同を得ておりますものの、充分な予算の裏付けがありませんとコアラボやコアファシリティーを設立・運営することは困難です。分子脳科学の班長をされています三品先生の呼びかけにより結成されましたマウスリエゾンというワークグループでは、そのあたりを何とかするべく議論を行っています。 とはいっても、まずは既にあるリソースでできることをしていく必要があります。私どもの研究室では、幸い統合脳の支援班からの補助も受けることができましたので、遺伝子改変マウスの網羅的行動解析についての共同研究の提案を歓迎しています。また、近いうちに、個々のマウスの行動の生データと「網羅的行動データ付き脳のリソース」の公開を行えればと考えています。ぜひ、このような考え・計画についての班員の皆様のご意見・ご要望をいただければと思います。 参考:宮川 剛, 「脳神経科学のlarge-scale化とマウスを用いた精神疾患の研究」, 実験医学 (羊土社, 2005), pp. 1152-1158.
|
||
|
(研究室で有する実験技術・リソースとその公開の可能性)
今のところ共同研究の依頼はすべて引き受けてきておりますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。ただ、飼育室のキャパシティーが限られておりますので、ご予約は早めにお願いいたします。網羅的行動テストバッテリーの詳細につきましてはホームページに掲載しております。
|
||