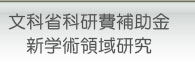
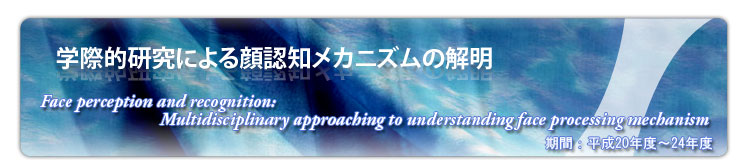
トップ > 公募要領
公募要領
本研究領域の目的は、「顔認知機能の解明」をキーワードとして、心理学、脳科学、医学、工学、情報学などの幅広い分野の学際的な研究者が集結して研究を進め、最終的には、可能な限りその成果を社会に還元することにある。
このため、下記の6つの公募項目について「計画研究」により重点的に研究を推進するとともに、これらに関連する研究に関して、2年間の研究を公募し、1年間の研究は公募の対象としない。研究分担者は置くことはできない。
公募研究の採択目安件数は、単年度当たりの応募額300万円を上限とする研究を14件程度、200万円を上限とする研究を15件程度している。公募項目A01とA02では主として健常人を対象とする。A03とA04は健常児・者に加え脳損傷例や発達期の障害を有する方を対象とする。A05は、非ヒト霊長類における顔認知の研究を推進するものが対象となる。A06では画像認識・生成技術を利用して顔認知の要因を明らかにする研究、およびそのデータ解析のためのソフトウェア開発等を対象とする。なお、化粧あるいは審美歯科に関する研究は顔認知には重要であり公募の対象とするが、内容によりいずれの公募項目に応募しても良いものとする。また、顔認知に直接関連する研究をこれまで行ってこなかったが、自身の関連領域の研究を応用することにより、顔認知研究を今後行おうとする野心的な提案も歓迎する。
このため、下記の6つの公募項目について「計画研究」により重点的に研究を推進するとともに、これらに関連する研究に関して、2年間の研究を公募し、1年間の研究は公募の対象としない。研究分担者は置くことはできない。
公募研究の採択目安件数は、単年度当たりの応募額300万円を上限とする研究を14件程度、200万円を上限とする研究を15件程度している。公募項目A01とA02では主として健常人を対象とする。A03とA04は健常児・者に加え脳損傷例や発達期の障害を有する方を対象とする。A05は、非ヒト霊長類における顔認知の研究を推進するものが対象となる。A06では画像認識・生成技術を利用して顔認知の要因を明らかにする研究、およびそのデータ解析のためのソフトウェア開発等を対象とする。なお、化粧あるいは審美歯科に関する研究は顔認知には重要であり公募の対象とするが、内容によりいずれの公募項目に応募しても良いものとする。また、顔認知に直接関連する研究をこれまで行ってこなかったが、自身の関連領域の研究を応用することにより、顔認知研究を今後行おうとする野心的な提案も歓迎する。
| A01 | 脳血流計測法(fMRI、PET、光トポグラフィー等)を用いた顔認知機能の解明 |
|---|---|
| A02 | 電気生理学的計測法(脳波、脳磁図等)を用いた顔認知機能の解明 |
| A03 | 顔認知障害の病態生理の解明とその治療法の開発 |
| A04 | 心理学、認知科学的研究による顔認知機能の解明 |
| A05 | 動物、特にサルにおける顔認知機能の解明 |
| A06 | 工学的手法による顔認知機能の解明 |
顔認知には後頭側頭葉、海馬、扁桃体、前頭葉など多くの脳領域の活動が伴う。この広範な脳活動をヒトを対象として計測するには、機能的磁気共鳴画像(fMRI)やポジトロン断層法(PET)を用いた脳賦活検査が必須である。さらに光トポグラフィーでは、日常生活に近い環境で実験を行うことが可能である。公募研究では、これらの非侵襲的脳機能計測法を用いた顔認知実験を主に健常人を対象として行う。
顔に関連する脳領域としては、紡錘状回(Fusiform Face Area: FFA)、視線認知に関わる上側頭溝(Superior Temporal Sulcus:STS)、さらに恐怖表情に反応する扁桃体などが重要である。これ以外にも意思判断に関わる前頭前野や、海馬と顔の記憶など対象となる研究領域は広い。これらの領域の神経活動を計測することで、顔認知の脳内メカニズムを探ることが目的である。実験課題は表情認知、親近性判断、自己他者顔、視線判断など、認知心理学の広い範囲にわたる。また対人コミュニケーションや、「心の理論」などに関わる研究も対象となるだろう。
公募班ではfMRI、PET、光トポグラフィーなどの主に脳の血行動態を計測する手法を用いて、これらの研究課題を推進する研究者を募集する。顔を用いた脳賦活検査や安静時の脳血流・代謝測定などで、脳内における顔認知の空間的・時間的情報を探る。またこれらの計測データを用いた、計算論的アプローチも含まれる。研究の一部には高解像度T1強調画像や拡散テンソル画像(DTI)など、解剖学的構造と顔認知の研究を含むこともできる。研究対象は主に健常人であるが、老年期の被験者を対象とした実験も含めてよい。またこれらの計測手法に精通し研究業績があれば、過去に顔認知に関わる研究を行ったことがなくとも応募することは可能である。
顔に関連する脳領域としては、紡錘状回(Fusiform Face Area: FFA)、視線認知に関わる上側頭溝(Superior Temporal Sulcus:STS)、さらに恐怖表情に反応する扁桃体などが重要である。これ以外にも意思判断に関わる前頭前野や、海馬と顔の記憶など対象となる研究領域は広い。これらの領域の神経活動を計測することで、顔認知の脳内メカニズムを探ることが目的である。実験課題は表情認知、親近性判断、自己他者顔、視線判断など、認知心理学の広い範囲にわたる。また対人コミュニケーションや、「心の理論」などに関わる研究も対象となるだろう。
公募班ではfMRI、PET、光トポグラフィーなどの主に脳の血行動態を計測する手法を用いて、これらの研究課題を推進する研究者を募集する。顔を用いた脳賦活検査や安静時の脳血流・代謝測定などで、脳内における顔認知の空間的・時間的情報を探る。またこれらの計測データを用いた、計算論的アプローチも含まれる。研究の一部には高解像度T1強調画像や拡散テンソル画像(DTI)など、解剖学的構造と顔認知の研究を含むこともできる。研究対象は主に健常人であるが、老年期の被験者を対象とした実験も含めてよい。またこれらの計測手法に精通し研究業績があれば、過去に顔認知に関わる研究を行ったことがなくとも応募することは可能である。
顔認知に関する脳波研究には長い歴史があり、現在も多くの研究者が研究を行っている。特に、ERPの顔特異的成分と称されるN170成分の研究が盛んであるが、さらに早い成分も関与している、という報告も増えてきた。また、背景脳波解析による、周波数分析やERD/ERSの研究も急速に増え新知見が報告されてきている。さらに15年ほど前より脳磁図による研究が始まり、脳波研究とは異なった観点からの研究や優れた空間分解能を利用した研究が多数報告されてきている。
公募班では脳波、脳磁図などの電気生理学的計測法を用いて、顔認知の研究を推進する研究者を募集する。時間分解能が非常に高いという長所を最大限に生かした研究を歓迎する。手術中の直接記録や、手術前に装着された慢性電極を用いた研究も本班の対象となる。またこれらの計測データを用いた、計算論的アプローチも含まれる。研究対象は主に健常人であるが、乳幼児や高齢者を対象とした発達関連の研究も歓迎する。またこれらの計測手法に精通し研究業績があれば、過去に顔認知に関わる研究を行ったことがなくとも応募することは可能である。
公募班では脳波、脳磁図などの電気生理学的計測法を用いて、顔認知の研究を推進する研究者を募集する。時間分解能が非常に高いという長所を最大限に生かした研究を歓迎する。手術中の直接記録や、手術前に装着された慢性電極を用いた研究も本班の対象となる。またこれらの計測データを用いた、計算論的アプローチも含まれる。研究対象は主に健常人であるが、乳幼児や高齢者を対象とした発達関連の研究も歓迎する。またこれらの計測手法に精通し研究業績があれば、過去に顔認知に関わる研究を行ったことがなくとも応募することは可能である。
「顔」は他者との識別や社会性の情報伝達において重要な身体部分であり、その認知障害は様々な場面での困難につながる。紡錘状回など多くの脳部位が関わる顔認知の機能に障害を示す成人における病態機序については一定の成果が得られ始めているが、小児では方法論的な問題もあり、解明するべき課題も多い。
公募班では、顔認知の障害を示す臨床例について、非侵襲的脳機能計測を用いた多面的アプローチにより病態生理解明をめざす臨床研究を募集する。対象年齢は、小児から成人まで幅広く考えていただきたい。すなわち、明らかな脳損傷を持つ場合の病変部位と顔認知機能障害との関連を明らかにする研究や認知能力にばらつきを示すものの形態的な異常を呈さない先天異常症候群もその対象となる。
広汎性発達障害など言語的・非言語的コミュニケーションに支障を示す発達障害児も研究対象となるので、小児期健常顔認知発達との比較に注目した研究も歓迎する。統合失調症、相貌失認などの精神・神経疾患群における顔認知、表情認知、視線認知の研究も審査対象となるが、行動学的検査・認知心理学的研究に加えてfMRI、PET、光トポグラフィー等の脳血流計測法や脳波、脳磁図等の電気生理学的計測法を駆使した研究も望ましい。幼弱期の脳から成人・老年期の中枢神経系での顔認知機能障害に関する客観的知見を集積することにより、社会生活を円滑に行うための支援をめざす研究も広く公募の対象となる。引きこもりに至ってしまった人たちの背景に顔認知障害がみられるのかどうかの研究も対象となろう。
上記の計測手法を障害児・者に適応した経験と研究実績があれば、過去に顔認知に関わる研究を行ったことがなくても応募することは可能である。
公募班では、顔認知の障害を示す臨床例について、非侵襲的脳機能計測を用いた多面的アプローチにより病態生理解明をめざす臨床研究を募集する。対象年齢は、小児から成人まで幅広く考えていただきたい。すなわち、明らかな脳損傷を持つ場合の病変部位と顔認知機能障害との関連を明らかにする研究や認知能力にばらつきを示すものの形態的な異常を呈さない先天異常症候群もその対象となる。
広汎性発達障害など言語的・非言語的コミュニケーションに支障を示す発達障害児も研究対象となるので、小児期健常顔認知発達との比較に注目した研究も歓迎する。統合失調症、相貌失認などの精神・神経疾患群における顔認知、表情認知、視線認知の研究も審査対象となるが、行動学的検査・認知心理学的研究に加えてfMRI、PET、光トポグラフィー等の脳血流計測法や脳波、脳磁図等の電気生理学的計測法を駆使した研究も望ましい。幼弱期の脳から成人・老年期の中枢神経系での顔認知機能障害に関する客観的知見を集積することにより、社会生活を円滑に行うための支援をめざす研究も広く公募の対象となる。引きこもりに至ってしまった人たちの背景に顔認知障害がみられるのかどうかの研究も対象となろう。
上記の計測手法を障害児・者に適応した経験と研究実績があれば、過去に顔認知に関わる研究を行ったことがなくても応募することは可能である。
ヒトを対象とした顔認知に関する心理学・認知科学的な実験研究はこの10年でたくさんの成果を生み出してきました。特に近年は顔認知障害との関連から、健常な顔認知メカニズムの解明とその獲得プロセス・学習プロセスの解明に重きが置かれています。
本研究領域では、ヒトの顔認知機能メカニズムの解明とその学習プロセスの解明に主眼を置いた、顔認知研究全般を広く行っていきます。 最近の研究から、顔認知の学習プロセスは発達初期の劇的な変化とともに青年期を越えて30代までを見越したより広い範囲の発達があるともいわれています。顔学習の特徴としてあげられる人種効果も、再学習が可能であることなど、顔の学習をより広範に取り上げる必要性が求められています。
こうした中で本研究領域では、ヒトを対象とした顔認知メカニズム全般の解明を目的とした研究、顔認知の基礎的なメカニズムの解明から、顔の社会的な側面に焦点をあてた、知覚認知心理学・認知科学的な実験研究を募集します。
顔認知の基礎的なメカニズムについては顔の学習や人種効果といった基礎的な顔認知メカニズムの解明研究があげられると思います。顔が他の物体を認識するときとは決定的に違う特徴をもつ、顔の既知性の効果などもあげられるでしょう。また、顔の社会的な側面については、表情や視線の知覚・認知メカニズムなどといったことがあげられます。このように本研究領域では、ヒトの顔認知メカニズムに関する幅広い研究内容について広く公募の対象とします。過去に顔認知の実験をしていたかにはこだわらず、むしろ現在の顔研究で見られるような「似たような研究内容の繰り返し」にとらわれることのない、新規な観点からの研究を歓迎します。
本研究領域では、ヒトの顔認知機能メカニズムの解明とその学習プロセスの解明に主眼を置いた、顔認知研究全般を広く行っていきます。 最近の研究から、顔認知の学習プロセスは発達初期の劇的な変化とともに青年期を越えて30代までを見越したより広い範囲の発達があるともいわれています。顔学習の特徴としてあげられる人種効果も、再学習が可能であることなど、顔の学習をより広範に取り上げる必要性が求められています。
こうした中で本研究領域では、ヒトを対象とした顔認知メカニズム全般の解明を目的とした研究、顔認知の基礎的なメカニズムの解明から、顔の社会的な側面に焦点をあてた、知覚認知心理学・認知科学的な実験研究を募集します。
顔認知の基礎的なメカニズムについては顔の学習や人種効果といった基礎的な顔認知メカニズムの解明研究があげられると思います。顔が他の物体を認識するときとは決定的に違う特徴をもつ、顔の既知性の効果などもあげられるでしょう。また、顔の社会的な側面については、表情や視線の知覚・認知メカニズムなどといったことがあげられます。このように本研究領域では、ヒトの顔認知メカニズムに関する幅広い研究内容について広く公募の対象とします。過去に顔認知の実験をしていたかにはこだわらず、むしろ現在の顔研究で見られるような「似たような研究内容の繰り返し」にとらわれることのない、新規な観点からの研究を歓迎します。
霊長類の脳には「顔」の情報処理に特化した神経回路が存在します.とくにマカクザルの側頭皮質では「顔」の視覚的呈示に対して特異的に反応する「顔」ニューロンが発見されており,サル脳におけるこのような「顔」関連ニューロン活動の記録・解析は,霊長類の脳における「顔」情報処理システムの解明に極めて重要な意味があります.
本研究領域では,非ヒト霊長類(non-human primates)を実験動物として用い,「顔」認知のニューロン機構の解明を目的とする,種々の神経科学的手法に基づいた野心的な研究を公募します.例えば,「顔」に基づいた表情認知や社会的認知を必要とする様々な認知課題を実際に行うサル側頭皮質・前頭皮質・頭頂皮質・大脳辺縁系(扁桃体など)・視床(視床枕など)等からの「顔」関連ニューロン活動や深部脳波の記録・解析等が対象になります.また,これら電気生理学的実験だけに限らず,サル各「顔」領域の解剖学的および機能的な神経結合を明確にすることを目的とする,各種トレーサーを用いた神経解剖学的研究やfMRIなど機能画像に基づく研究,「顔」情報処理システムの物質基盤の解明を目的とする種々の行動薬理学的研究,および種々の認知課題に対して微小破壊法や可逆的機能脱落法を用いた神経心理学的研究等も公募の対象とします.
また,本研究領域では,比較認知論的立場から非ヒト霊長類の「顔」に基づいた表情認知や社会的認知を特徴づけ,ヒトの表情認知や社会的認知との関係を明確とすることを目的とする霊長類学的研究も広く公募します.
本研究領域では,非ヒト霊長類(non-human primates)を実験動物として用い,「顔」認知のニューロン機構の解明を目的とする,種々の神経科学的手法に基づいた野心的な研究を公募します.例えば,「顔」に基づいた表情認知や社会的認知を必要とする様々な認知課題を実際に行うサル側頭皮質・前頭皮質・頭頂皮質・大脳辺縁系(扁桃体など)・視床(視床枕など)等からの「顔」関連ニューロン活動や深部脳波の記録・解析等が対象になります.また,これら電気生理学的実験だけに限らず,サル各「顔」領域の解剖学的および機能的な神経結合を明確にすることを目的とする,各種トレーサーを用いた神経解剖学的研究やfMRIなど機能画像に基づく研究,「顔」情報処理システムの物質基盤の解明を目的とする種々の行動薬理学的研究,および種々の認知課題に対して微小破壊法や可逆的機能脱落法を用いた神経心理学的研究等も公募の対象とします.
また,本研究領域では,比較認知論的立場から非ヒト霊長類の「顔」に基づいた表情認知や社会的認知を特徴づけ,ヒトの表情認知や社会的認知との関係を明確とすることを目的とする霊長類学的研究も広く公募します.
顔認知のメカニズムを探ろうとするこれまでの多くの研究では、現実の人物の顔やその顔写真を視覚刺激として被験者に提示し、それらから被験者に認知される感性情報をさまざまな実験心理学の手法を駆使して計測することで、顔のもつ物理情報と人に認知される感性情報の関係を明らかにしようとしてきた。しかし、実際の人物の顔や写真の見え方は、極めて多くの要因が重畳した複雑な多様性を呈しているため、心理実験において視覚刺激とする顔パターンの変動要因を統制することはなかなか困難であった。これに対して、近年、コンピュータによる画像の認識・生成技術の成熟を背景として、顔自体が有する物理的特徴やその観察条件の変動によって生じる顔パターンの見え方を規定するパラメータを抽出するとともに、これらを自在に制御することによって統制された多様性をもつ顔の視覚刺激が得られるようになった。これにより、顔の見え方を規定しているさまざまな物理的要因とその顔から観察者に認知される感性情報との関係を定量的にモデル化することが可能となってきている。
本公募班では、上記のようなアプローチによって、視覚刺激としての顔パターンの物理的特徴とその顔から認知される感性情報との因果関係を明らかにすることで、人間による顔認知過程のモデル化を推進する研究者を募集する。とくに、人物の個人性、属性、感情、関心、意図、印象、発話など、人間が顔の視覚パターンから読み取っているさまざまな情報について、個別のモデル化のみならず、それら相互の関連性に着目した研究を歓迎する。また、加齢による顔貌変化のモデル化とその応用に関する研究も歓迎する。
本研究の遂行には、コンピュータによる画像の認識・生成技術を中心とする工学的手法ならびに実験心理学的手法の双方を駆使した学際的な取り組みが不可欠であるが、自らの研究の軸足をこのいずれか一方のみにおいている研究者であっても、共同研究等によるこのような学際的研究の実績ならびに今後の具体的計画が明確である場合については、応募を大いに歓迎する。
さらに、顔認知の研究のために、fMRI, NIRS, EEG, MEGなどを用いて記録された膨大な記録の解析のためには、新しいソフトウェアの開発が必要と考えられる。本班では、このような研究の応募も大いに歓迎する。
本公募班では、上記のようなアプローチによって、視覚刺激としての顔パターンの物理的特徴とその顔から認知される感性情報との因果関係を明らかにすることで、人間による顔認知過程のモデル化を推進する研究者を募集する。とくに、人物の個人性、属性、感情、関心、意図、印象、発話など、人間が顔の視覚パターンから読み取っているさまざまな情報について、個別のモデル化のみならず、それら相互の関連性に着目した研究を歓迎する。また、加齢による顔貌変化のモデル化とその応用に関する研究も歓迎する。
本研究の遂行には、コンピュータによる画像の認識・生成技術を中心とする工学的手法ならびに実験心理学的手法の双方を駆使した学際的な取り組みが不可欠であるが、自らの研究の軸足をこのいずれか一方のみにおいている研究者であっても、共同研究等によるこのような学際的研究の実績ならびに今後の具体的計画が明確である場合については、応募を大いに歓迎する。
さらに、顔認知の研究のために、fMRI, NIRS, EEG, MEGなどを用いて記録された膨大な記録の解析のためには、新しいソフトウェアの開発が必要と考えられる。本班では、このような研究の応募も大いに歓迎する。
Copyright (C) 2008 kaoninchi. All Rights Reserved.