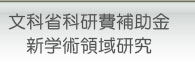
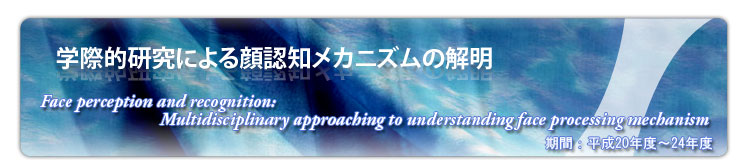
トップ > 研究概要
研究概要
| 本領域研究の背景 |
| 本領域研究の目的 |
近年、心理学、脳科学、基礎医学、臨床医学、工学、情報学などの幅広い分野で、「顔認知機能」の研究が非常に盛んになってきた。顔認知は言語認知と並んで、人間が社会生活を送る上で最も重要な機能と考えられるようになってきたからである。人間の乳幼小児期においては、母親の顔を他のものと区別することは生存上、最も重要な機能の1つであろう。これは人間のみならず動物が生まれつき持っており、かつ生存するために不可欠の能力と考えられる。成長するにつれて、親だけではなく様々な「顔」に関する認知過程の発達と成熟は社会的生存において極めて重要となってくる。特に人間にとっては「社会的コミュニケーション」を取る手段としての意義が大きい。顔認知が他の一般的な物の認知と明らかに異なっている点の1つとして、例えば「丸いものがふたつあると目に見えてしまう」というように、あるパターンを見るとそこに顔を見出すという特殊な認知過程の存在が考えられる。
実際、顔認知機能の障害は社会生活に歪みをきたすだけでなく、教育現場においても様々な問題を生じている可能性がある。特に自閉症の子供達や、引きこもりなどの状況に陥る学童での顔認知機能の障害の可能性が指摘されている。また、ゲームなどに多くの時間を費やし、対人関係にかける時間がだんだん短くなっている現代の子供達においての、顔認知機能の発達障害、例えば相手の表情から気持ちをうかがい知る能力の低下、などの可能性も重要な問題となりつつある。
以上のような状況をふまえ、欧米諸国、特に米国では、顔認知に関する研究者は急激に増加しており、発表論文の数も年々増加の一途をたどっている。特に近年の、脳波、脳磁図、機能的磁気共鳴画像(fMRI)、近赤外線分光法(NIRS)といった非侵襲的Neuroimaging手法の飛躍的な進歩により、人間が顔を認知する脳内メカニズムが次第に明らかになりつつあることも、若手研究者の急速な増加につながっている。残念ながら現在、日本では欧米に比して、顔認知機能の研究は質量共にかなり劣っている。しかし、若手の間では顔認知機能の研究に興味を持つ研究者が急速に増えてきた。この時期にこそ、心理学、脳科学、基礎医学、臨床医学、工学、情報学などの学際的な研究分野の研究者が集結して、新しい学術領域を開拓し、この重要なテーマの解明に力を注ぐことが重要であると考えられる。領域代表者の知る限り、これまで「顔認知」をテーマとした大規模な研究班が組織されたことは無く、非常に斬新な申請と考えている。さらに、多くの公募班員をつのり、研究内容が偏らず斬新なアイディアが次々に生まれてくることを期待している。「顔認知」をテーマとして、このような研究グループが組織されることは、国内はもちろん諸外国にも例が無く、極めて独創的かつ斬新な企画と考えている。
本研究領域の目的は、「顔認知機能の解明」をキーワードとして、心理学、脳科学、医学、工学、情報学などの幅広い分野の学際的な研究者が集結して研究を行い、最終的には、可能な限りその成果を社会に還元することにある。その目的のために以下のような点を研究の大きな柱として掲げたい。もちろん、これらは独立したものではなく、互いに重複している部分も少なくない。
- 1.『顔認知機能の初期発達過程を明らかにする
(児童・小児心理学者)』 - 2.『小児における顔認知障害の病態生理を明らかにする
(小児科医、精神科医)』 - 3.『自閉症における顔認知障害の病態生理を明らかにする
(児童・小児心理学者、小児科医、精神科医)』 - 4.『成人における顔認知機能の様々な心理学的側面を明らかにする
(心理学者、認知科学者)』 - 5.『成人における顔認知機能の脳内メカニズムを明らかにする
(脳科学者、認知科学者)』 - 6.『顔認知障害の病態生理を明らかにする
(神経内科医、精神科医、脳神経外科医)』 - 7.『サルを対象として、顔認知の脳内メカニズムを詳細に解明する
(基礎医学者、脳科学者)』
上記のような研究には、最新のテクノロジーを駆使した画像技術や解析技術が必須である。工学系研究者の協力無しでは、研究の新たな展開はありえない。幸い、日本では、工学系研究者によって、コンピュータ技術を駆使した様々な顔の造形や表情変化を可能にする技術が発達している。また、化粧品を製造する企業を中心として、顔に様々な変化をつけた場合に、それが他の人からどのような評価を受けるか、といった研究も盛んである。現代において化粧の役割はけっして軽んじてはならず、現代の顔認知研究には、特に女性顔の認知に関する研究には必須の問題であろう。そのため、以下の項目も研究目標として掲げる。
- 8.『コンピュータによる様々な顔の造形技術の進歩(工学者)』
- 9.『化粧による顔認知の変化の研究(工学者、認知科学者)』
本学術領域研究の研究対象は、「既存の学問分野の枠に収まらない新興・融合領域の創成をめざすもの」、「異なる学問分野の研究者が連携して行う共同研究等の推進により、当該研究領域の発展を目指すもの」、「多様な研究者による新たな視点や手法による共同研究等の推進により、当該研究領域の新たな展開を目指すもの」、そして「学術の国際的趨勢等の観点から見て重要であるが、我が国において立ち遅れており、当該領域の進展に格段の配慮を必要とするもの」に該当し、新学術領域研究の主旨に極めて合致したものであると考えられる。
これまでは、人文系研究者(心理学等)、基礎医学者、臨床医学者、脳科学者、認知科学者、工学者が一同に会して、一つの大きな研究テーマに取り組んできた例は非常に少なく、本領域の研究の発展が、今後の学際的研究の模範的な例になれば、その効果は極めて大きいと考えられる。
本研究領域の主要目標は、顔認知の発達過程を詳細に解明すること、顔認知が社会生活における役割を考察すること、顔認知障害の原因解明とその治療法の開発を行うこと、顔認知に関連する脳内部位の特定を行うこと、である。そして、得られた研究成果を社会に還元すること、特に教育現場における様々な問題の解決の一助となること、が最終的な目標である。