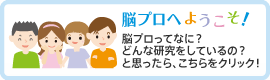
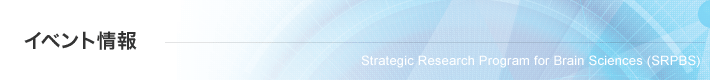
| 「脳科学研究を支える集約的・体系的な 情報基盤の構築(神経情報基盤)ワークショップ」 日 時 : 平成22年6月2日(水) 13:30~16:10 会 場 : 東京大学理学部1号館 小柴ホール 主 催 : 文部科学省 プログラム付き抄録集はこちら 新規課題説明資料はこちら |
 104 名の方にお集まりいただきました。 多数のご来聴ありがとうございました。 |
|
|
|
 |
INCFはOECDの勧告に基づき2005年に設立された。我が国もこれに対応すべく文科省の要請により、理研・脳科学総合研究センターに神経情報基盤セ ンターを立ち上げ(http://www.neuroinf.jp/)、現在、日本ノードとして、視覚科学、無脊椎動物脳、マウス小脳発達トランスクリプ トーム、包括脳(旧統合脳)、脳イメージング、動的脳などのプラットフォームを公開・運用している。講演では、そうしたINCFと日本ノードの発足、その 後の経緯、展開を紹介する。日本ノードは世界に先駆け、全日本体制で展開してきた。日本ノードは、国際機関であるINCFをささえる日本の機関として脳プ ロを支援し、日本における研究成果を世界に効率的に情報発信することが使命である。特に、脳プロが短期決戦のプロジェクトである関係上、その成果を残す意 味でも、脳プロの成果を日本ノードを通じて世界に発信することを義務付けるのが適当と考える。各位と共に,我が国の新しい展開を期待したい。 |
 |
ショウジョウバエは他のモデル生物に比べてもコミュニティによる研究基盤整備が充実しており、世界最大のストックセンターが京都にあるなど日本が果たしている役割も大きい。我々は1995年以来、インターネット最古の脳神経データベースのひとつFlybrainを運営しており、2010年には拡張性に富んだプラットフォームにハエ脳の既知の全ての神経種の情報を網羅した新サイトFlybrain Neuron Databaseを公開した。我々がストックセンターに提供した数千に上る遺伝子発現誘導系統の発現パターンデータなど公開を期待されている情報も多く、今後の展開の可能性について報告する。一方、神経のデータベースを15年間提供してきて、情報基盤整備に関する一般的な認識にはギャップを感じることも多い。データベースは論文に使ったデータの残りを集めるというやり方では作ることは難しく、むしろ情報基盤整備と論文による成果発表は利害が相反する面すらある。あまり触れられることのないこれらの課題についても話題を提供したい。 |
 |
脳の分子、遺伝子、神経回路など様々なレベルで得られる膨大なデータを、人間の知能や情動とその病変の理解と改善へとつなげていくためには、異なるレベルでの実験的知見を階層的な定量モデルとして統合し、その計算機シミュレーションにより動作を解析し予測することが不可欠である。そのためには、遺伝子ネットワーク、細胞内シグナル伝達系、ニューロンの電気化学的コンパートメント、局所回路、感覚と行動をつなぐ全脳回路など、異なる物理スケールと基礎方程式を持つ数理モデルを連結し、効率よくシミュレーションを行いその予測精度の評価を行う手法の確立が求められる。また、すべてのレベルの詳細データを人間から得ることは非現実的であり、分子、遺伝子、細胞、回路などそれぞれの実験に適した種からのキメラ的なデータを統合してシステムを構築し、データの出所の違いを考慮してパラメタ推定を行う手法の開発も必要である。本講演では、これらに関して今日利用可能なデータやモデリング手法のサーベイを行い、今後必要かつ有望な研究開発の方向について提言することを試みる。 |
 |
パネリスト(左から) : 銅谷 賢治 (沖縄科学技術大学院大学) 伊藤 啓 (東京大学) 臼井 支朗 (理化学研究所) 山元 大輔 (東北大学) 森 郁恵 (名古屋大学) 宮川 剛 (藤田保健衛生大学) |