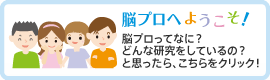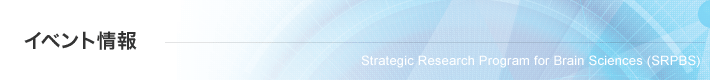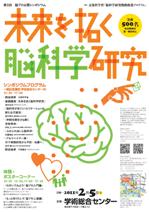◇開催趣旨 昨今、脳科学に対する社会の関心が高まるとともに、医療や教育といった社会への貢献が期待されています。本プログラムではこのような背景を踏まえ、研究成果を社会に還元するだけではなく、脳科学研究の現状、発展状況を皆様にお知らせし、ご意見を伺うことも重要なミッションであると考え、プログラムが発足した2008年度より年に1回、公開シンポジウムを開催してまいりました。
今回で3回目となります本シンポジウムを通して、現在の脳科学研究はどのようなものか、また今後どんなことをやらねばならないか、ということを少しでもご理解いただくとともに、皆様のご意見やご要望、ご批判をいただく機会にできればと考え開催いたしました。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
◇開催の辞 文部科学省より、文部科学審議官の森口泰孝氏が開会のご挨拶を申し上げました。

◇基調講演 : 「未来を拓く脳科学研究」
|

|
津本 忠治
文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」
プログラムディレクター
理化学研究所脳科学総合研究センター
シニアチームリーダー
|
津本忠治プログラムディレクターが本プログラムの概要説明に加え、脳科学の歴史的推移や最新技術の進捗状況、また今後の展望などについて講演を行いました。
◇講演1 : 「BMIが拓くリハビリテーションの新たな可能性」

|
里宇 明元
慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室
教授
|
肢体不自由の方々を支援するための革新的医療技術を開発・実用化することは、ご本人の日常生活、生活の質の向上と社会参加の促進をもたらすだけでなく、社会全体の医療・介護に係わる負担を軽減するうえで重要です。ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)は、脳機能の一部と機械を融合させ、外界を操作するための技術であり、その臨床応用が実現すれば大きな福音となることが期待されます。
われわれは、2008年より文部科学省脳科学研究戦略推進プログラム課題A「日本の特長を活かしたBMIの統合的研究開発」の拠点のひとつとして、非侵襲型BMIの開発とリハビリテーション臨床への応用を担当し、これまでに以下の成果をあげてきました。
1)少ないチャンネル数で得た脳波から運動イメージに関連した情報を高精度に取り出す信号処理方法を考案し、実用レベルの脳波BMIを開発しました。これを用いて、インターネット上の仮想世界セカンド・ライフ内のキャラクタを念じただけで制御することに健常者、筋ジストロフィー、頸髄損傷者で成功するとともに、運動イメージで手関節と手指を動かすことが可能な電動装具を開発しました。
2)脳波BMIと電動装具を用いたBMIニューロフィードバック・トレーニングにより、従来、治療が困難であった重度片麻痺上肢の機能回復が得られる可能性があることを見出しました。現在、症例数を増やしながら、その効果を臨床スケール、脳機能イメージング、電気生理学などの手法を用いて検証するとともに、効果をより強めるための手法の検討および効果のメカニズムを解明するための研究を進めています。
BMI技術の確立と臨床応用により、失われた機能の代償にとどまらず、中枢神経の可塑性を誘導し、障害そのものを回復させるような、新たなリハビリテーションが展開していくことが期待されます。
◇講演2 : 「神経回路をひも解く技術革命」
|

|
伊佐 正
自然科学研究機構生理学研究所発達生理学研究系
認知行動発達機構研究部門 教授
|
脳の神経回路は実に複雑である。よく電気回路に例えられるが、多種類の素子が様々な相手と接続し、様々な信号を伝達し、情報が処理される。このような回路の機能を調べるために、これまでに行われてきた実験手法は、主に刺激・記録・破壊であった。
脳の特定の部位を電気刺激して、手が動けば、その部位は何らかの形で手の動きに関わっていると考えられる。その部位の神経細胞の活動を記録して、手の動きに関連する活動が観察されれば、その部位と手の動きとの相関はわかる。その部位を破壊して、手が動かなくなれば、その部位は手の動かすことに必要だとはわかる。しかし、脳の回路を電気刺激すると他の場所からそこに送られてくる線維も刺激されてしまう。記録の場合も相関はわかるが因果関係はわからない。また破壊にしても、神経回路が電子回路と違って厄介(本当は良いことなのだが)なことに、破壊してから時間が経つとどんどん勝手に修復機能が働いてしまう。脳科学者は長年このような問題に悩まされ続けてきた。本当は「何らかの形で関わっている」以上のことを知りたいのに、まるで核心に近づけないもどかしさがあった。
近年の分子生物学の進歩が急速にこのような問題を解決しつつある。まずマウスで遺伝子改変を行うことで、脳の特定の細胞に発現するタンパク質のプロモーターと呼ばれる配列を使って特定の細胞だけを破壊したり、活動を変化させたりできるようになった。特に、最新兵器は光で神経活動を操作できる分子を使って、神経細胞の活動をミリ秒単位の正確さで操作できる技術で、optogenetics(光遺伝学)と呼ばれている。これらの手法は遺伝子改変が比較的容易なマウスやゼブラフィッシュのような動物では可能になってきたが、本当にヒトの高次脳機能を知りたい研究者にとってはサルのような動物で使えるようになってほしい。またヒトの治療に使う可能性を考えれば、せめてサルでうまくいってくれなくてはいけない。特にニホンザルのような動物では当面は遺伝子改変動物の作製よりはむしろ、ウィルスベクターを使って遺伝子導入を行うことが現実的である。脳科学研究戦略推進プログラムでは、サルへの遺伝子導入にチャレンジしてきた。マウスとは違った困難が待ち受けていたが、今や、サルでも神経回路機能を操作するツールが開発されつつある。
◇講演3 : 「心のふれあいと脳科学」
|

|
定藤 規弘
自然科学研究機構生理学研究所大脳皮質機能研究系
心理生理学研究部門 教授
|
我々はいかにして社会的存在となるのか?この発達社会心理学的な問いは、急激な少子化、学級崩壊、引きこもり多発などから、大きな社会的関心を集めています。社会能力とは、他人の性質や意図を正確に認知するための情報処理過程と定義され、その発達は、他者との関係において子どもの示す行動パターン、感情、態度ならびに概念と、それらの経時的な変化として観察されますが、その神経基盤および発達期における獲得過程については不明の点が多いのです。近年、機能的磁気共鳴画像(機能的 MRI)による非侵襲的脳機能画像の発達が、ヒト脳の神経活動を観測することを可能にし、社会能力を含む高次脳機能の解明には欠かせない手段となっています。
本講演では、機能的MRIについて概説したのちに、自他同一性から、自他区別、共感と心の理論の発達を経て向社会行動(利他行為)へ至る、というモデルに基づき社会能力の発達過程を解明する試みについてお話します。特に人間の利他的行為において社会的承認(褒め)が重要であること、そしてそれが基本的報酬や金銭報酬と同様の神経基盤をもつことが明らかとなりました。さらに、社会能力発達の重要な指標である共同注意の神経基盤を2個体同時fMRI計測によって明らかにする取り組みについて紹介し、個体を対象とした従来のイメージング研究から、複数個体間の相互作用の神経基盤を探るという、新たな研究方向を展望します。最後に、ヒトの社会能力について物質レベルから行動レベルに至る統合的理解を目指すために、ミクロからマクロレベルにいたるまで各階層で進行している神経科学の成果を人文諸科学と結びつけていくことが重要であること、その結節点としてのイメージング研究の重要性を論じます。
◇講演4 : 「アルツハイマー病:分子病態研究から予防・治療へ」
|

|
岩坪 威
東京大学大学院医学系研究科神経病理学
教授
|
高齢化社会の本格化に伴い、本邦の認知症患者数は200万人にのぼり、その2/3はアルツハイマー病(AD)が原因と考えられている。ADは記憶障害を始めとする種々の認知機能を冒し、進行性の認知症を来す神経変性疾患である。ADの病因に関する研究は、脳に生じる病理学的変化の分析、ならびに家族性AD病因遺伝子の解析を両輪として発展した。とくに老人斑として脳に蓄積するβアミロイドは(1)ADに特異性が高い(2)AD脳に最初期に生じる病変である(3)家族性ADの病因遺伝子APP及びプレセニリン(PS)の変異により凝集性の高いAβ42の産生が亢進する、などの理由から、βアミロイド蓄積過程をADの病因と考えるアミロイド仮説が幅広く支持され、根本的治療法(disease-modifying therapy)の治療標的として有力視されている。
ADの分子レベルでの病態研究の進展に伴い、β、γセクレターゼ阻害薬によるAβの産生抑制、Aβの除去を促進する免疫療法などが開発され、臨床試験も開始されているが、治療効果の実証は難渋している。アミロイドの蓄積は、認知機能障害の発症に10年以上先行して生じることを考慮すると、アミロイド抑制療法などのdisease-modifying therapyが予防・治療効果を発揮するためには、より早期の軽度認知障害(MCI)の時期, 更には臨床症状の発現前(preclinical AD)に先制的に治療を開始することが理想的である。このためには、MRIやPETスキャンなどの画像診断、脳脊髄液などの生化学バイオマーカーを指標として、ADの進行過程と薬効を評価する方法を確立することが必須となる。このような目的でAD Neuroimaging Initiative (ADNI)などの大規模臨床研究が米国、本邦で進行中である。
近年、AD発症の危険因子として糖尿病などの代謝症候群が注目されている。疫学的研究により、耐糖能異常を呈する人のAD発症危険率は健常者の2倍以上に上昇し、早期からアミロイド蓄積が生じることも判明した。ADの危険因子の作用メカニズムを解明し、その回避を図ることは、ADの予防と健康な老いの実現につながる。本プログラムで推進する、AD発症機序におけるインスリン作用異常に関する研究についても言及する。
◇閉会の辞 中西重忠プログラムディレクターより閉会の辞を申し上げ、本シンポジウムを終了いたしました。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

374名の方にご参加いただきました。多数ご来場いただき誠にありがとうございました。
<体験・ポスターコーナーの様子>* 展 示 *
|
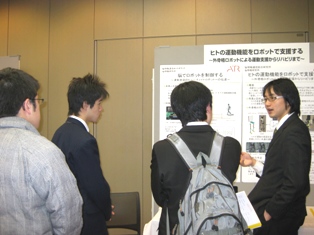
|

|
1.ヒトの運動機能をロボットで支援する~外骨格ロ
ボットによる運動支援からリハビリまで~(ATR) |
2.ブレイン・マシン・インターフェースの臨床応用を目指した医工連
携プロジェクト-「機能代償システム」から「治療システム」へ-
(慶應義塾大) |
|
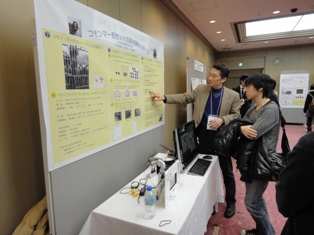
|

|
3.コモン・マーモセットの認知機能を調べる方法の
紹介(京都大霊長類研究所)
|
4.社会性をつかさどる行動特性・神経基盤の解明
(生理研)
|
|
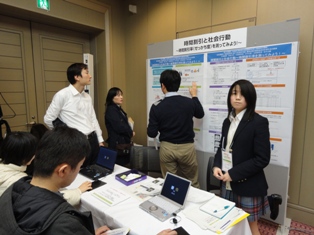
|

|
5.時間割引と社会行動~時間割引率(せっかち度)
を測ってみよう!~ (大阪大) |
6.うつ病を克服しよう
(精神・神経医療研究センター) |
|

|
7.障害者自立支援のためのBMI型環境制御システム(障害者リハビリテーションセンター研究所)
※「健康大国日本」の実現に向けたライフ・イノベーションの推進のために、各府省連携による効率的な取組が望まれています。こうした連携の一環として、厚生労働省から最近の研究成果をプレゼンテーションしていただきました。 |
* ポスター *
体験・ポスターコーナーも多くの方にお越しいただき大盛況でした、誠にありがとうございました。
今回は新しい試みとして、玉川学園高等部の「サイエンスコミュニケーター」の皆様にお手伝いいただき、ご来場者の方々へ脳プロの研究やスーパーサイエンスハイスクール活動での成果などを紹介していただきました。
また、脳プロの最新成果をまとめたポスターをそれぞれ展示し、研究者がポスターの前に立って、詳しく内容を説明したりご来場者からのご質問にお答えしました。
今後も様々な企画を催したいと存じますので、来年度の公開シンポジウムも宜しくお願い申し上げます。
(高柳)