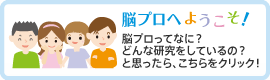
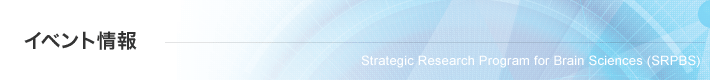
| 「精神・神経疾患の克服を目指す脳科学研究 (健康脳)ワークショップ」 日 時 : 2011年2月8日(火) 10:00~15:00 会 場 : 東京医科歯科大学 M&Dタワー2階講堂 主 催 : 文部科学省 プログラム付き抄録集はこちら 新規課題説明資料はこちら 参考)平成23年度「脳科学研究戦略推進プログラム」予算案 |
 161名の方にご参加いただきました。 ご来場誠にありがとうございました。 |
|
笹木竜三文部科学副大臣 |
金澤一郎先生 |
|
|
「広汎性発達障害、統合失調症、気分障害の共通病態」 現在の精神疾患の疾患分類は、DSMなどの症候学的な操作的診断基準が使われており、病態研究も、DSMに則った各疾患の病態を解明することが企図されてきた。しかし、診断基準に含まれていない認知機能を例にとると、広汎性発達障害、統合失調症、双極性障害に共通して障害される機能は多い。 大規模で精密な家族研究によれば、統合失調症と双極性障害の発症には共通の遺伝因子が関与してい ることが報告された(Lancet 373,9659p234-9,2009)。さらに、近年のゲノム研究により、発達障害と統合失調症に共通するCNVが同定され、GWASの結果から統合失調症と双極性障害に共通するSNPが報告されている。したがって、病態の重複部分を念頭においた検討が、解明に至る道筋には必須と考えられる。本ワークショップでは、広汎性発達障害、統合失調症、気分障害の共通病態を考え、今後の病態研究の方向性を考えてみたい。 |
|
|
「発達障害の克服を目指す脳研究の抱える問題点、困難さについて」 発達障害の克服には、“遺伝要因による脳の発生異常”と“環境要因による脳の機能障害”の相関を解明することが必須である。そのためには、あらかじめ優れた作業仮説を設定し、基礎研究で得られる知見と臨床研究で明らかになる事象を科学的に結び付けることが最重要である。加えて、倫理面での問題を早い時点で解決しておくための組織作りが不可欠である。臨床研究の障壁は、①均一な患者集団を特定することの困難さ、②倫理的な困難さ、のふたつである。加えて、ヒトを対象とした脳研究の常套手段である脳イメージングから得られるデータのS/N比は低く、有意な結論を得ることが困難な場合も多い。また、我が国で使われている小児の高次脳機能評価法は必ずしも世界標準として認められているものではない。さらに、介入による効果を判定するには多くの被検者と長い観察期間が必要となる。個々の研究チームの力もさることながら、それらの絶妙な組み合わせと、優れたオーケストレーションが成功の鍵となる。 |
「臨床研究の基盤の上での精神疾患のバイオマーカーの探索」 我が国の年間自殺死亡者数は1998年に急増し、自殺総合対策会議(内閣府)、厚生労働省、各自治体の取り組みにもかかわらず、その後年間3万人を下回ることなく推移している。このような状況において、うつ病に代表される精神疾患の治療法の洗練と開発は喫緊の課題である。薬物および非薬物 治療法を包含した実践的な多施設臨床試験体制を確立し (Furukawa et al., Br J Psychiatry, 2006)、その研究基盤の上でそれぞれの疾患および治療反応性と関連するバイオマーカーを探索することが、一つの現実的な戦略であろう。また、精神疾患の病態の複雑さを考慮すると、バイオマー カーの探索は、動物モデルから推測される分子・細胞レベルの指標のみではなく、脳のシステムレベルでの指標も広く視野に入れることも重要であろう (Lui et al., Arch Gen Psychiatry, 2010)。 |
「うつ病克服のための脳科学研究戦略」 現在のうつ病の病態研究は、症状横断的なDSM診断により対象選択している反面、臨床では様々な亜型やその異種性が指摘されており、この乖離がうつ病の病態解明を混乱させている。うつ病発症には遺伝的要因、養育環境などによる脳機能の異常が関与するが、その分子病態として、BDNF異常仮説などいくつか提唱されている。一方、脳機能解析研究により、うつ病の神経回路異常所見も蓄積されつつあるが、分子病態との関連性は不明な点が多い。本質的なうつ病克服には、「うつ病の症状は、 どの神経回路で、どのような分子病態により生じるか?」を明らかにする必要がある。研究戦略としては、うつ病の臨床症状、分子病態マーカーと相関する神経回路を特定し、病態に基づく新たな亜型 分類を構築すること。これに対応するモデル動物作製を試み、その分子病態や行動所見とうつ病の臨床所見、死後脳所見との整合性を厳密に検証して、より本質的病因に迫る新規バイオマーカーの探索、 根本的治療法の開発へと展開し、臨床に還元することが重要であろう。 |
「我が国における認知症研究の進展と展望」 超高齢社会にある我が国の認知症患者数は230万人と推計され、その約6割がアルツハイマー病といわれている。老化に伴って脳病変が変化する鍵がアミロイドβタンパク質(Aβ)の蓄積であり、 ネプリライシンのバランス崩壊が提唱されている。もう1つの脳病変は神経原線維変化であり、リン酸 化タウ、ユビキチン、シヌクレイン分子を発見してきた本邦の功績は揺るがし難い。これらの研究は、その後のパーキンソン病研究の突破口あるいはTDP-43の発見にも連動している。γセクレターゼの活性化機構の解明やイプシロン部位の同定などユニークな研究も見逃せない。アルツハイマー病仮説は、アミロイド仮説からAβオリゴマー仮説へシフトされつつあるが、オリゴマー反応を促進させる大阪変異の発見は、世界に発信した研究成果として評価されている。Aβオリゴマーを中心とした病因論の解明を軸とした基礎および臨床研究が展開すると考えている。 |
「脳老化関連疾患、特に認知症性疾患の克服を目指して」 脳老化関連疾患、特に認知症性疾患を克服する戦略を立てるため、問題提起等を行う。認知症全体の過半数を占めるAlzheimer病(AD)は、分子病態解明研究の成果に基づき早期診断法や治療薬の開発が行われてきたが、根本的治療薬については現在までに臨床試験で有効性が証明されたものはない。 発症に影響する遺伝的あるいは環境的なリスク・防御因子については多くの報告がある。特にライフスタイルに関わる因子(食事、運動、生活習慣病)は予防介入の対象として注目される。それらの作用機序解明、それに基づく予防介入試験等を推進する必要がある。AD以外の変性型認知症には、Lewy 小体型認知症(DLB)、前頭側頭葉変性症(FTLD)、神経原線維変化型老年期認知症(SD-NFT)、嗜銀顆粒性認知症(AGD)などがある。それらの分子病態解明研究を推進する必要があり、それが画期的診断法や根本的治療法の開発につながるものと考えられる。 |
「精神・神経疾患の克服に向けた脳科学研究の倫理的課題」 精神・神経疾患の領域における脳科学研究を、社会と調和した形で推進していくためには、脳科学研究全般に関わる倫理的課題の検討に加え、精神・神経疾患の領域に特異的な課題に取り組む必要がある。そこで本シンポジウムにおいては、これまでの脳プロ内でのわれわれの活動を紹介するとともに、今後、精神・神経疾患の克服に向けた脳科学研究を本格的に推進する上で検討すべき課題を提示し、その解決に必要な対応について検討してみたい。具体的には、これまでの活動として、1)説明同意文書の標準化、2)偶発的所見への対処法に関する提言、3)脳プロ倫理相談窓口、の3点について触れる。次に今後検討すべき課題として、同意能力の問題など、精神・神経疾患の領域に特異的な 倫理的・法的・社会的課題を示し、その解決の道筋を考えたい。 |
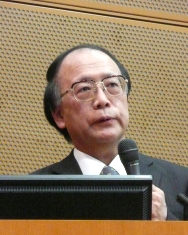 |
「わが国の精神・神経疾患研究の発展のためには独自の死後脳バンクの構築が必要」 福島医大・神経精神医学講座では1997年より精神疾患研究のための死後脳バンクの構築を進めてきた。希望のあった国内外14施設に対して、審査のうえ福島医大・神経精神医学講座との共同研究としての研究計画に標本提供を既に行った。精神疾患の病態解明と効果的治療法の開発のためには実際の患者脳についての研究が欠かせないことは明らかである。しかし、わが国を含むアジア諸国では精神疾患研究のための体系的死後脳バンクは福島と国立病院機構リソース・ネットワークを除いて構築さ れていない。その原因は、欧米とアジアでの死後脳に対する人々の考え方の相違、精神疾患解明のた めに脳研究が必要という認識を持ちにくいこと、精神疾患患者の死因は身体疾患によることが普通であり精神科医が剖検を提案する機会を持ちにくいこと、である。生物学的精神医学会・ブレインバンク設立委員会では、バンク設立のために必要な倫理指針の検討など体制作りを進めつつある。福島バンクの経験では患者・家族の積極的理解と参加が献脳促進のために欠かせない。また、献脳希望者を増やす啓発と広報の独自の努力、全国を網羅するネットワークの構築、安定した財源確保の促進が必須である。うつ病、発達障害、統合失調症など実際の患者脳の研究体制が整うことで、わが国の精神疾患研究が欧米に負けない水準に発展すると期待される。 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|