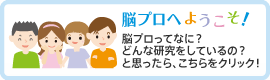
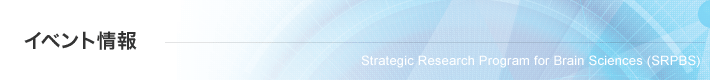
| 脳プロワークショップ ブレイン・マシン・インターフェースの 実用化に向けて -利用者・市民の立場から 日 時 : 2012年9月29日(土) 13:30-17:00 場 所 : 東京国際フォーラムホールD7 (〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1) 主 催 : 文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」 ※プログラム付き抄録集はこちら ※アンケート結果はこちら ※ワークショップ報告書はこちら(2.96MB,PDF形式) |
 |
板 倉 康 洋 文部科学省 研究振興局ライフサイエンス課 課長 |
 |
| <講演①> 「BMIリハビリテーションの新たな可能性」 里 宇 明 元 慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室 教授 |
 |
| 肢体不自由者を支援するための革新的医療技術を開発・実用化することは、ご本人の日常生活・生活の質の向上と社会参加のために重要です。BMIは、脳機能の一部と機械を融合させ、外界を操作する技術であり、その臨床応用が実現すれば大きな福音となると期待されます。 私たちは文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」に参画し、脳波を用いたBMIの開発とリハビリテーションへの応用を担当し、以下の成果を上げてきました。 1)頭皮上脳波から運動イメージに関連した情報を高精度に取り出す信号処理方法を考案し、実用レベルの脳波BMIを開発しました。これを用いてインターネット上の仮想世界セカンド・ライフ内のキャラクタを念じただけで制御することに成功するとともに、運動イメージで手関節と手指を動かすことが可能な電動装具を開発しました。 |
2)脳波BMIと電動装具を用いたリハビリテーションにより、従来、治療困難であった重度片麻痺上肢の機能回復が得られる可能性があることを見いだしました。現在、症例数を増やしながら、その効果を臨床評価、脳機能イメージング、電気生理学などを用いて検証するとともに、効果メカニズムを解明するための研究を進めています。 BMI技術の確立と臨床応用により、失われた機能の代償にとどまらず、中枢神経の可塑性を誘導し、障害そのものを回復させるような新たなリハビリテーションが展開することが期待されます。 本シンポジウムでは、私たちの研究成果について、またリハビリテーションの立場からBMI技術の今後の展開についてお話ししました。 |
|
|
|
| <講演②> 「低侵襲型BMIによる運動、 コミュニケーションの再建」 吉 峰 俊 樹 大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科 教授 |
 |
| 私たちは、「脳の信号(脳波)を解読する」ことにより、その人がどのような運動をしようとしているのか、その意図を読み取り、それに従ってコンピュータや周辺の機械を動かせるシステムの開発を目指しています。頭皮の上からではなく、脳の表面から記録する「脳表脳波」を用います。電極を入れるときに皮膚や骨を一度「きず」付けることになりますので、「侵襲的」と言われます。ただし、脳自身には「きず」を付けないため、その程度は低い、つまり「低侵襲的」と呼ばれています。 現在のところ、手や腕の動きの一部について解読することができます。「手を握る、開く」、「チョキをする」、あるいは「肘を曲げる、伸ばす」といった単純な動作です。しかし、これにより、「考えるだけで」、「コンピュータのカーソルを左右上下に動かす」、「ロボットハンドを操作する」ことができます。 |
私たちは、実際に筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者さんにとってこのシステムが「安全で、うまく使えるものかどうか」を確かめる試験(臨床研究)を始める予定です。今の段階ではこのシステムを長期間にわたって使用することはできません。電極のコードが皮下を通って体外につながっているためです(有線式)。今回の「臨床研究」が問題なく進めば、次の段階として「埋め込み型」ワイアレス装置(無線式)を開発し、自宅で使用できる実用的なシステムができると考えています。 本シンポジウムでは、以上の低侵襲型BMIの研究成果について詳しくご紹介させていただきました。 |
|
|
|
| <講演③> 「非侵襲型BMIによる障害者自立支援」 神 作 憲 司 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 脳機能系障害研究部 脳神経科学研究室 室長 |
 |
| 私たちは、脳波を用いた非侵襲型BMIの研究を行い、特定の視覚刺激に注目している際に生じる脳由来信号を利用してワープロや環境制御を可能とするシステムを開発しています。このシステムに用いる視覚刺激の強調表示の手法として、これまでの輝度変化に加えて色変化(緑/青)を用いることで、使用感及び正答率を有意に向上させることに成功しました。また、当該課題遂行中のEEG-fMRI信号を計測したところ、右の頭頂後頭部を中心として、輝度変化に加えて色変化(緑/青)を用いたことによる特徴的な脳活動が見いだされました。 私たちは、このシステムの実用化に向けて、着脱容易で長時間使用可能な脳波電極、独自の脳波計及びソフトウェア等を開発しています。 |
これまで、頸髄損傷者がこのシステムを健常者と同様に操作可能であることを示し、さらに現在はALS患者を中心とした実証研究を進めています。 また、将来技術として、これらのBMI技術と拡張現実(Augmented Reality: AR)技術を統合させ、AR-BMI技術も開発しました。これにより、操作者の環境を脳からの信号で制御するこれまでのBMIに加えて、代理ロボットを介してのリモート環境を制御することも可能です。こうしたBMI技術を更に研究開発していくことで、麻痺を伴う患者・障害者の活動領域拡張に貢献していくことが期待できます。 本シンポジウムでは、私たちが開発した技術についての進捗、及び将来期待できる応用についてお話ししました。 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
江 藤 文 夫 国立障害者リハビリテーションセンター 総長 |
 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本ワークショップでは、まずBMIの技術開発に取り組む研究者から、最新の研究状況を報告いたしました。次に、パネリストの方々から利用者の立場で、BMI実用化に向けたニーズや期待についてお話しいただきました。それらを踏まえ、最後は、研究者、パネリスト、会場の参加者の皆様からの質問を交え、BMIの実用化に向けた課題と展望に関するディスカッションを行い、様々な貴重なご意見をいただくことができました。
また、会場ロビーには、日本大学、慶應義塾大学、大阪大学、国立障害者リハビリテーションセンター研究所によるBMI研究の展示コーナーを設置しました。実際のBMI機器に触れていただくデモンストレーションも併せて、ご来場の皆様に最新の研究について詳しく説明させていただきました。
当日はたくさんの方にご参加いただくとともに、活発なご質問・ご意見をいただきました。BMI実用化への期待の大きさを改めて強く感じるとともに、現場のニーズを研究者に届ける場の重要性を再確認することができました。ご参加いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。
(大塩)