第4回 ブレインマシンインターフェース —川人光男教授の研究— (4)
2008.9 vol.5
東京大学 立花隆ゼミ 酒井寛
脳の研究って、一体何のためなの?
いきなり質問です。一体、何の為に脳を研究するでしょうか?みなさん考えた事ありますか?このシリーズでいろんな脳についての研究を紹介してきました。そのいろんな研究を見渡した時、私は「人間を知る為に脳を研究している」のだというのが答えの一つだと思います。今回紹介する川人光男先生の研究は、人間を知る為、脳の働きを知る為になんとロボットをつかって研究しているというこれまで紹介して来たものとは違う切り口の画期的な研究です。ロボットをつかって人間を知る?それはどういう事なのでしょう?
驚くべき川人先生の研究
川人先生はロボットを用いて人間を理解すために様々な研究を行ってきました。その中から1つ、すごい成果を紹介します。
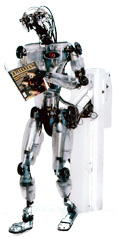
「自分で学習するロボット“DB”」です。川人先生は脳のなかでも小脳という、生き物の動きをコントロールしている脳に注目し、「小脳内部モデル理論」という理論を提案しました。この理論は行動を学習するときの小脳
の働きを説明したものです。小脳のなかには何種類かの神経が存在していて、おおまかに体に行動を命令する神経、実際にからだがどういう行動をしたのかを小脳に伝える神経、そして想い描いていた行動と実際の行動の差をみつけて、その差をなくそうとする神経の3つに分けられます。そしてそれらが相互作用した結果、行動を真似して身につけることができるという理論です。これは川人先生が小脳の実験観察を繰り返す中でたどり着いたものなのです。かなり難しいですね。わからない人は他人の行動を真似して学習する時小脳の中で何が起こるのかを説明したもの、と思ってもらえれば十分です。この仕組みのおかげで私たちは泳げなかったのが泳げるようになるなど、身体を使う動きの学習・上達が可能になるのです。
この理論の大きなハードルは、「理屈はわかったのだが本当にそのとおりなのか実際に試す事が出来ない」という事でした。そこで川人先生は理論が正しい事を証明するため、小脳内部モデル理論に基づいて行動を学習するロボットを作り上げました。このロボットはDBと名付けられ、ロボットなのに手のひらの上で棒を立てる動作など30種類ちかくの行動を、自分で観察して真似することで学習しました。これはびっくりですね。このようにしてロボットを使う事で川人先生は人間が新しい行動を学ぶときに脳のなかで何が起きているかを解明したのです。
BMIってなんだ?
みなさんにとってBMIというアルファベットは見慣れないものと思います。これはBrain Machine Interfaceのことで脳(Brain)の機能を機械(Machine)で補助、調整(Interface)するという意味です。今、このBMIが注目されていて、ロボットと人間の関わり方を大きく変えてしまう可能性を秘めています。BMIには様々なものがあります。耳が聞こえなくなった人に機械を埋め込んで再び聞こえるようにする技術は既に使われています。川人先生はBMIについても研究していてそれはとても大胆なものです。脳からある行動をするときの脳波などの信号を取り出し、その信号を利用してロボットを動かそうという試みなのです。実際に川人先生はアメリカの研究者たちと協力して、画期的な実験を成功させました。アメリカにいるサルの脳に電極をとりつけ、サルが動くときに出る脳の中の電気の流れをキャッチします。そしてそれを日本の川人先生の研究所まで送信し、その信号に従ってヒト型ロボット(名前はCBiといって、せいりけんニュースVol.3で紹介されています)が動くということに成功したのです。
ところでこの技術は一体何に将来的に使えるのでしょうか?今、主に考えられているのが福祉利用です。脳に障害があるため体が自由に動かせない人の脳から体を動かす信号をとりだし、それを機械に伝える事で体を動かす補助をする事が考えられています。また、遠くは慣れた場所でも現地にいる自分の姿をしたロボットで行動するなんてことも出来るかもしれません。そうすると自分は家にいてロボットがかわりに学校に行く、なんて夢みたいな(笑)生活が出来るかもしれませんね。しかしいい事ばかりでもないようで、軍事利用されるという可能性も秘めています。この技術を本当に人の役に立つ、社会の役に立つように使う、その使い方が重要ですね。
ロボットと人間の新しい素敵な関係
「自分で行動して判断する知性のあるロボットをつくりたい」と語る川人先生。川人先生のこれまでに行った研究によって、人間にとってのロボットが大変重要なものになりました。人間の脳の仕組みを理解する上では重要だし、さらにはBMIというロボット技術によって人間の生活を豊かにするかもしれない。そんな可能性が川人先生によってもたらされたのです。「人を知る為には脳を知らなければいけない。脳を知る為にはロボットは大事な役割をする」と語る川人先生。これから先、ロボットを用いた脳の研究で私たち人間についてどんな面白い、びっくりするような発見が生まれるのか、とても楽しみですね!
- 「第12回 久保義弘教授研究室の研究 ~純粋におもしろいんだよ~」2011.1 vol.19
- 「第11回 燃料センサー「AMPK」と肥満ホルモン「レプチン」」2010.9 Vol.17 PART.3
- 「第11回 肥満ホルモン「レプチン」と睡眠ホルモン「オレキシン」」2010.5 Vol.15 PART.2
- 「第11回 "生活のリズム"をつくる脳の働き」2010.3 Vol.14 part1
- 「第10回 生き物らしさとは何か?」2010.1 vol.13
- 「第9回 記憶を細胞から調べるってどういうこと?(9-後)」2009.11 vol.12
- 「第8回 記憶を細胞から調べるってどういうこと?(9-前)」2009.9 vol.11
- 「第7回 "見る"の仕組みを"見る" (8)」2009.7 vol.10
- 「第6回 脳の動きを見る —定籐先生の研究— (7)」2009.5 vol.9
- 「第5回 脳の左右差の原因は一体何なのか?—篠原先生の研究— (6)」2009.3 vol.8
- 「第4回 ブレインマシンインターフェース —川人光男教授の研究— (4)」2008.9 vol.5
- 「第3回 研究は道楽 —柿木隆介教授の研究— (3)」2008.7 vol.4
- 「第2回 瀬籐光利先生の研究 ~長生きしたい!~」2008.5 vol3
- 「第1回 Hot(ホット)は辛い? -富永真琴教授の研究ー」2008.3 vol.2
