斉藤修,増保生郎,伊藤政之(東京都神経科学総合研究所,長浜バイオサイエンス大学)
斉藤実(東京都神経科学総合研究所)
柳川右千夫(群馬大学大学院医学系研究科)
石原健(九州大学大学院理学研究院)
久保義弘(生理学研究所)
近年の味覚研究によって,多くの味覚の受容にG蛋白質共役型受容体(GPCR)が関与していること,更に苦味受容体 T2Rファミリー,甘味・うま味の受容体T1Rファミリーなどの存在が明らかになって,味覚シグナルの概略が知られるようになってきた。しかし,古くから 知られる味覚の順応については,分子的な機構はまだほとんど明らかにされていない。
これまでに,GPCR系の調節因子としては,RGSとGRKのファミリーなどが発見されてきた。RGSは,三量体G 蛋白質の活性化されたGαに結合してその不活性化を促進するGAP作用を持つ分子群で,一方GRKは受容体をリン酸化するキナーゼファミリーであり,両因 子ともGPCR系に抑制的に作用して脱感作などを引き起こす。本研究では,味細胞に,味覚順応を引き起こすRGSやGRK分子が存在するものと考え,それ らの探索を試みた。
味細胞は舌上に極少数で,さらに細胞株は樹立されていない。一方,ごく最近,胃や腸などの消化器官で舌と同じ仕組み で苦味物質を感知しているらしいこと,さらに小腸由来の培養細胞STC-1が,舌で発見された苦味受容体を発現していることが報告された。そこで私たち は,このSTC-1細胞に注目して,まずこの細胞が,実際に苦み物質に味細胞と同様に応答できるのかどうかを検討した。細胞内カルシウムの変動を指標に解 析した結果,STC-1細胞が舌で応答のみられる種々の苦み物質に顕著に応答することが確認された。そこで,このSTC-1細胞をモデルに,味覚順応に関 わると期待される如何なるRGSとGRKファミリーが存在するのか,混合プライマーPCR法で検索した。その結果,STC-1細胞にRGS9とGRK2が 発現されていることが明らかになり,さらにはそれらが実際に舌組織の味細胞にも存在することが判明した。
そこで,次にRGS9とGRK2が,味覚応答をどう調節するのか,STC-1細胞に高発現させ,その効果を解析し た。結果,RGS9に関しては,実験がまだ進行中である。一方,GRK2については,その発現によって特定の苦味応答が抑制される事が判明した。即 ち,GRK2の味覚順応への関与が初めて示唆されることになった(Chem.Senses 30:281,2005)。今後は,さらにSTC-1細胞をモデルに味覚情報とその調節機構に関する研究を進めていきたい。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
発表論文
馬場広子,山口宣秀,林明子,梶ヶ谷仁志,鈴木彩佳,星登美子,高橋ゆかり,山田早織(東京薬科大学)
山田真久(理化学研究所脳科学総合研究センター)
渡辺修一,中平健祐(埼玉医科大学)
中平英子,長谷川明子(国立精神・神経センター神経研究所)
清水健史(熊本大学発生医学研究センター)
朴華(九州大学大学院医学研究院)
有髄神経軸索では,興奮の発生に関与する電位依存性ナトリウムおよびカリウムチャネルはランビエ絞輪周辺に局在化す る。この特徴的な分布にはミエリン膜と軸索の間のparanodal junction (PJ)が深く関わっている。我々はこのPJの形成にミエリン膜糖脂質のスルファチドおよび4回膜貫通タンパク質であるCD9が関与することを明らかにし てきた。また,PJの異常によってどのような分子が変化してくるのかを,遺伝子発現およびタンパク質レベルで解析した。まず,PJが欠損した場合の神経細 胞上の遺伝子発現の変化を明らかにするため,野生型およびスルファチド欠損マウス間でサブトラクションライブラリーを作成した。この結果,スルファチド欠 損マウスで減少しているcDNA7個,増加しているcDNA11個見いだし,本年度これらの遺伝子を同定した。さらにこれらの発現部位および変化をin situ hybridizationで解析した。PJを欠損した場合のタンパク質レベルでの変化を明らかにするために,22週齢スルファチド欠損および野生型マウ スの脊髄ホモジネート(膜,可溶性画分)を2次元電気泳動し解析した結果,スルファチド欠損マウスで明らかに増加するもの4個および減少するもの1個を見 出し,質量分析により同定した。増加するものの一つheat shock protein 27 (HSP27)に関してさらに解析したところ,4週齢では変化なく,チャネルが消失する22週齢で明らかに増加していることがわかった。抗体を用いた組織 染色の結果,軸索上のチャネルの局在変化の時期に一致してアストロサイトの活性化が生じ,白質部分の活性化アストロサイトのみにHSP27が増加している ことが明らかになった。
和田洋巳,田中文啓,佐久間圭一郎,柳原一広(京都大学大学院医学研究科)
長谷純宏,長束俊治,石水毅,青木孝文,伊東伸子,橋本周子,藤原由加里(大阪大学大学院理学研究科)
梶本哲也(京都薬科大学有機化学系)
佐々木紀彦,神山伸(創価大学工学部)
山中龍也,土屋尚人(新潟大学脳研究所)
神奈木玲児(愛知県がんセンター研究所)
大平敦彦(愛知県コロニー発達障害研究所)
中北愼一(香川大学総合生命科学実験センター)
辻崇一(お茶の水大学大学院糖鎖科学研究教育センター)
東海林博樹(香川大学医学部)
本家孝一(高知大学医学部)
鈴木邦彦(東海大学未来科学技術共同研究センター)
N-結合型糖鎖は主に細胞表面に存在し,他の細胞や細胞外基質との相互作用を介して数々の重要な機能を果たすことが知られている。我々はこれまでにマウスの正常発達過程やヒトのがん,神経変性疾患などを対象に糖鎖の発現パターンの研究を行ってきた。
我々はB16(マウスメラノーマ細胞)を用いて肺転移と肝転移モデルを作成し,両者の糖鎖パターンの比較から α1,6-フコース構造が肺転移に特に多いことを見出した。同構造を認識するレクチンであるLCA (Lens culinaris agglutinin)によって同構造を多く持つ細胞集団と少ない細胞集団をB16からフローサイトメーターでソーティングしてマウスの尾静脈から注入し たところ,前者の集団は有意に多くの肺転移結節を形成したことから,α1,6-フコース構造は肺転移において重要な機能を持つことを報告した。本年度,ヒ ト臨床病理標本のLCA染色を行い,ヒトにおいても肺転移をした癌組織にα1,6-フコース構造の多いことを見いだした。
α1,6-フコース構造は正常の肺にも非常に多く見られる糖鎖構造である。この研究は,臓器の特徴的糖鎖構造がその臓器への癌転移を促進する可能性を示唆しており,非常に興味深いといえる。
また,癌の糖鎖解析を肝癌,グリオーマに関しても行い,特徴的な糖鎖パターンのあることを見いだした。
清水惠司,中林博道,土屋孝弘,八幡俊男,豊永晋一,中居永一,朴啓彰(高知大学医学部)
栗山茂樹,出口章広,峠哲男,池田和代(香川大学医学部)
中根恭司(関西医科大学)
中村秀次(兵庫医科大学)
グリオブラストーマは原発性脳腫瘍の約10%を占める,非常に悪性度の高い脳腫瘍である。グリオブラストーマは高い 増殖性と浸潤性を特徴とし,発見されたときには広範に進展しており,手術技術や放射線照射技術の進んだ現在でも,完全な治療は困難である。また,化学療法 もこの10年間進歩は見られず,それゆえに新しい治療法の開発が待たれている。
近年,グリオブラストーマにおいて,オリゴデンドロサイト前駆細胞に特異的に発現する転写因子Olig1,2が発現 していることが報告された。オリゴデンドロサイト前駆細胞は脊髄の発生過程において腹側の限局した部分から発生し,脊髄全体に移動するという高い機動性を 持つ。我々はこの性質がグリオブラストーマの高い浸潤性に関与しているのではないかと考えた。
グリオブラストーマでのOlig1,2の発現を組織染色で調べるため,まずヒトOlig1,2に対する抗体の作成を行った。ヒトOlig1,2のアミノ酸配列において抗原性の高いと予想される部位に相当する抗原ペプチドを合成し,ウサギから抗血清を得た。
また,Olig1,2を発現しているグリオブラストーマでは,Olig1,2発現以降の正常な分化経路に異常があ り,それが幼若な性格の維持に関与している可能性がある。特にOlig2遺伝子は運動ニューロンとオリゴデンドロサイトの発生に必須であるため,分化経路 を正常化することにより腫瘍細胞を分化誘導できるのではないかと考えた。そこで我々は,Olig2の関与する細胞分化の分子的機構を明らかにするため,時 期特異的遺伝子組み換え法であるCreERTM/loxPシステムを用いてマウス胎仔において細胞系譜解析を行った。我々はすでにOlig2の遺伝子座にCreERTMをノックインしたマウスを作製している。このマウスを,CreERTM依 存的な組み換えによって,永久的にlacZ遺伝子を発現するマウスと掛け合わせることにより,特定の時期にOlig2を発現している細胞を追跡できるダブ ルトランスジェニックマウスを作製した。そして解析の結果,これまでOlig2陽性細胞からは運動ニューロンとオリゴデンドロサイトのみが発生してくると 考えられていたが,それ以外にアストロサイトや上衣細胞も生じてくることを見出した。今後は,Olig2を発現しているグリオブラストーマ細胞に,分化誘 導因子を発現させ,腫瘍細胞が分化していくかどうかを検討する。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
発表論文
関係論文
阿部輝雄(新潟大学脳研究所)
白尾智明(群馬大学医学部)
河西春郎(生理研)
大脳皮質の錐体細胞樹状突起のスパインは2光子励起観察法やGFP導入の導入により,形態や更にその機能の変化の長 期的追跡が可能となってきている。我々は,更に,2光子励起グルタミン酸法によって,スライス培養標本において単一スパインの形態可塑性を誘発することを 可能とし,これに機能変化が伴うことを見出している。シナプス可塑性に関わる分子・超分子のダイナミズムが可視化定量化するための分子標識法,有効な追跡 分子,標本の選択などについて検討を行ってきた。本年度はこの手法を用いて,スパイン形成に重要と考えられているドレブリンを強制発現させ,スパイン形態 や動態の変化を観察した。その結果,ドレブリン発現により異常に大きなスパインの出現を見るが,ほとんどのスパイン形態は正常であること,しかしながら, このスパインをグルタミン酸で刺激してもほとんどスパイン頭部増大が見られなくなることが明らかとなった。スパイン頭部増大に係わるシグナル分子に異常が あることが推察された。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
発表論文
関係論文
酒井哲郎(琉球大学医学部・形態機能医科学講座生理学第2分野)
岡田泰伸
膜電位感受性色素を用いた細胞膜電位活動の光学測定法とCaイメージングを組み合わせた複合的光学測定システムの開 発を目指した共同研究プロジェクトの第一段階として,本年度はまず,膜電位の光学測定をおこなうための基本的測定システムのセットアップをおこなった。作 製した測定システムの概要は次の通りである。
測定システムの光学系には生理研のOlympus IX71型倒立顕微鏡を用い,光源はタングステン・ハロゲンランプを直流安定化電源で点灯し,入射光の安定化をおこない,干渉フィルタ(700, 620, 570 nm,朝日分光製)を介してステージ上の標本に照射した。×4の対物鏡と×3.3の写真用接眼鏡で作られる実像面にあわせて受光素子を置き,標本からの透過光の強度の変化を記録した。
受光素子にはフォトダイオード(Bell & Howell 509-10型)を用い,出力は利得×2000の増幅器(自作)により増幅し,周波数可変型アクティブフィルタ(fc = 20 Hz, NF回路設計ブロック製)を通してオシロスコープで記録をおこなった。
ラット心房標本をmerocyanine-rhodanine系膜電位感受性色素NK2761で染色し,ステージ上 に置き,電気刺激を与えながら刺激により誘発される活動電位の光学測定をおこなった。なお,心筋収縮にともなうアーチファクトを抑制するため,細胞外液に 筋収縮抑制剤として2,3-butanedione monoxime (BDM, 20 mM)を添加した。
得られた光学的シグナルを図に示す。シグナルは波長700 nmで活動電位に対して透過光の減少(吸光度の増大)を示し,620 nmでシグナルが消失し,570 nmでシグナルの方向が逆転するという膜電位感受性色素特有の波長依存性を示している。
今年度の共同研究により,膜電位感受性色素を用いた膜電位の光学測定のための最も基本的セットアップを作製すること が出来た。今後このシステムをより実用的なものとするためには,蛍光膜電位感受性色素の導入や,Caプローブとの組み合わせの開発などの課題が残されてい る。これらを次年度の課題として共同研究を進めていきたい。
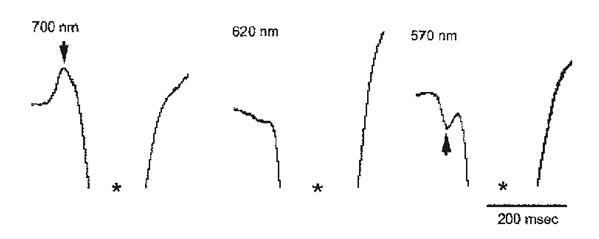
図 ラット心房標本から得られた光学シグナル。波長700,620,570 nmでの測定。矢印は活動電位由来の光学シグナルを示す。*の部分は筋収縮由来のアーチファクトのため振り切れている。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
関係論文
松山 善次郎,橋爪 龍磨,犬塚 貴(岐阜大学医学部)
井本 敬二
アルツハイマー病に代表されるいわゆる変性性神経疾患では,いろいろな病態メカニズムにより神経細胞が細胞死に陥る。しかしその際,細胞内のCa2+代謝が,細胞死に行くかそれとも細胞死を食い止めるかの運命決定に関係しているのではないかと推測されている。
われわれはこれまでにCa2+チャネル変異マウスの解析を進めてきたが,これらの変異マウスでは一般的にCa2+チャネルの機能が低下することから,一般的に考えられているCa2+のオーバーロードが細胞死を招くのではなく,むしろCa2+流入量の減少が細胞障害に関係するのではないかと考えてきた。
本実験では,培養細胞系でCa2+代謝障害のモデルを構築し,Ca2+代謝を変えることにより細胞死がどのように変わるかを検討した。
BHK細胞に正常のP/Q型Ca2+チャネルもしくはC末にグルタミン酸リピートを持つP/Q型Ca2+チャネルを導入した。通常の培養条件では細胞死の率に差異は見られなかったが,serum starvation,Cdk阻害,高カリウム外液による脱分極という条件では,細胞死の率に差を認めた。正常Ca2+チャネルによる細胞死防止効果は,P/Q型Ca2+チャネルの特異的な阻害剤であるωアガトキシンIVAにより減弱した。
これらの結果より,ある特定の条件化では,Ca2+チャネルを介して流入するCa2+が細胞死を防止する役割を果たすと推測される。
竹内 倫徳(東京大学大学院医学系研究科)
宮田 麻理子(神経シグナル研究部門)
部位時期特異的ノックアウト法を用いることにより,発生期の回路網形成と成体のシナプス可塑性,運動学習とを切り離 して解析することが可能である。グルタミン酸受容体(GluR)δ2はプルキンエ細胞(Pu)のみに発現し,特に,小腦平行線維(PF)-Pu細胞間シナ プス後膜に局在し,PFのシナプス形成や小腦LTDに重要な働きをする分子である。本共同研究では成体でのGluRδ2の機能を予定するため,誘導型 GluRδ2欠損マウスを用い,小脳の平行線維(PF)-Pu細胞間のシナプス特性,および,シナプス長期抑圧(LTD)を調べる目的で共同研究を開始し た。GluRδ2を成体Pu細胞でのみ欠失させるために,C57BL/6系統由来の3種類のマウスの作製((1)小脳Pu細胞特異的にCrePR*(組換 え酵素Creと変異型プロゲステロン受容体ホルモン結合領域との融合蛋白質)を発現するDCPマウス,(2)組換え酵素FLP発現マウス, (3)GluRδ2のエクソンの両端にCre認識配列loxPを導入したGluRδ2マウス)を行った。これら3種類のマウスの交配を行いfGluRδ2 遺伝子とDCP遺伝子の両方を有するマウスを作製し,薬剤誘導によりGluRδ2蛋白が90%減少することができた。しかしながら,充分な欠損までに薬剤 投与後少なくとも3-5ヶ月かかることから,高週齡マウスの脳スライスでの,ホールセルパッチクランプの解析に困難を極め,安定したLTDの測定には至ら なかった。PF-Pu細胞間シナプスの基本的な電気生理学的解析を行い,短期シナプス可塑性(short-term depression)は概ね野生体と同じく正常であった。
八木 健,平林敬浩,金子涼輔(生理学研究所 高次神経機構)
先崎浩次,野口由起子(国立精神神経センター神経研究所)
江角重行,雲出 佑,内村有邦(大阪大学大学院生命機能研究科)
多様化したプロトカドヘリンα遺伝子群(Pcdha/CNR)は中枢神経系に多く発現している。そのゲノム構造は, 免疫グロブリン(Ig)やT細胞受容体(TCR)遺伝子と同様に,多数の可変領域エキソンと1組の定常領域エキソンを含んでおり,ニューロンの識別にこの 多様性が利用されている可能性がある。これまでの研究により,Pcdha遺伝子はそれぞれの可変領域エキソンが片側対立染色体に由来しており,また複数の 組合せ発現をしていることが示された。Pcdha遺伝子のもつ多様な可変領域エキソンで対立遺伝子が組み合わさって発現することは,脳におけるニューロン の独自性を特徴づけるための機構である可能性がある。そこで,このユニークな発現様式を動物個体レベルで解析することを目的とし,各可変領域エクソンの上 流にEGFP,HcRedなどの蛍光タンパク質遺伝子をノックインした遺伝子改変マウスの作製を行った。現在までにCNRv6およびCNRv11可変領域 エクソンの上流に蛍光タンパク質遺伝子をノックインしたマウス作製が終了しており,その他の可変領域エクソンについても作製が進行している。今後はこれら のマウスを交配することでを発現を制御する機構を明らかにする予定である
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
発表論文
関係論文
高田昌彦(東京都神経科学総合研究所)
泰羅雅登(日本大学大学院総合科学研究科)
南部 篤
大脳基底核の機能を考える上で,大脳皮質との相互連絡,さらには大脳皮質間の線維連絡を知ることが重要である。従来 の考え方では,随意運動の際には,前頭連合野からまず前補足運動野・帯状皮質運動野吻側部に神経情報が流れ,更にそこから補足運動野・運動前野・帯状皮質 運動野尾側部を介して一次運動野に情報が流れると考えられていた。今回,これらの領域に標識物質を注入し,線維連絡を詳細に検討したところ,前頭連合野か ら前補足運動野・帯状皮質運動野吻側部への直接投射は弱く,むしろ運動前野吻側部に投射していることがわかった。また,運動前野吻側部は前補足運動野・帯 状皮質運動野吻側部・運動前野尾側部に投射していることもわかった。これらのことから随意運動に際しては,前頭連合野→運動前野吻側部→補足運動野・帯状 皮質運動野尾側部→一次運動野,あるいは前頭連合野→運動前野吻側部→運動前野尾側部→一次運動野という経路によって情報が運ばれると考えられる。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
発表論文
関係論文
稲瀬 正彦,中陦 克己(近畿大学医学部)
森 大志(山口大学農学部)
南部 篤
最近ヒトを対象とする脳機能画像法を用いた研究から,二足歩行の実行に関与する高次脳領域が注目を集めている。しか しこれらの結果から,賦活された脳領域がどのような歩行運動の機能的側面を制御するかという問いに答えることはできない。ニホンサルは流れベルト上で二足 歩行を学習できる。我々の糖代謝陽電子撮影法を用いた研究から,このサルの歩行中には一次運動野をはじめとする複数の大脳皮質運動関連領域が賦活されるこ とが明らかとなってきた。本課題では二足歩行の大脳皮質制御機序の解明を目的として,無拘束サルの一次運動野から二足歩行中の神経活動を導出記録した。そ してその神経活動の修飾様式から,一次運動野の歩行制御における機能的役割の解明を試みた。
1頭のニホンサルを対象とし,一次運動野の下肢領域から歩行中の神経活動を記録した。記録にはタングステン電極を装 着した4チャンネルマイクロマニピュレータを用いた。マニピュレータを1~2週間にわたり頭蓋上へ固定し,各電極を数百μm/日ずつ進めることにより discriminationが可能なユニット活動を記録した。神経活動の記録に同期して歩行するサルをビデオ撮影(250 frames/s)した。流れベルトの速度は0.7~1.5m/sの範囲で変化させた。記録部位に対しては皮質内微小電気刺激を行った。得られたビデオ画 像から歩行周期(遊脚相および着地相)を決定し,神経活動の修飾様式を歩行周期と流れベルトの速度変化に対応させて解析した。
無拘束の状態で導出された神経活動の殆んどは2時間以上にわたり安定して記録された。一次運動野から記録された神経 細胞はすべて,歩行周期に伴いphasicまたはtonicにそれらの活動を修飾した。phasicに活動した神経細胞は1~2峰性の修飾パターンを示し た。これらの修飾活動は歩行周期において主に着地相に認められたものが多く,遊脚相にみられた活動は比較的少なかった。記録された神経活動の多くは,流れ ベルトの速度の増加に伴ってそれらの発射頻度のピーク値を増加させた。
以上の結果は歩行制御において一次運動野が,下肢のリズム運動の制御に歩行周期を通して関与すること,特に着地相に おける体幹荷重の支持および推進力の生成に関わる可能性を示唆しており,サルの大脳皮質がネコなどのsubprimateとは異なる様式で単純な歩行運動 を制御することが示唆された。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
発表論文
伊 藤 功(九州大学大学院理学研究院)
本共同研究により,我々は成獣マウス海馬神経回路に構造的・機能的非対称性が存在することを,はじめて分子レベルで 明らかにした。この成果は米科学誌Science(2003年)に掲載され,脳の左右差に明確な分子基盤の存在を示した研究として高く評価されている。 我々は最近NMDA受容体サブユニットのノックアウトマウスを用い,上記の事実をさらに生理学的,解剖学的にも証明した。
我々の結果は,脳はその構造的階層性の各レベルで様々な非対称性を持ち得ることも示唆している。脳内で明確な左右差 を示すタンパク質分子が明らかにされたことにより,これを指標として,今後は(a)脳の機能的,構造的非対称性が何時,どのようにしてできあがるのか。 (b)左半球と右半球の神経細胞を特徴づけている性質は何か。(c)左と右という性質は複雑な脳の構造を作り上げ,それを適切に機能させるためにどのよう な意味があるのか。等の問題を明らかにすべく,分子レベルから行動レベルまでの研究を統合的に実施する計画である。
川口泰雄(生理学研究所・大脳神経回路論研究部門)
小林和人(福島県立医科大学・生体情報伝達研究所)
柳川右千夫(群馬大学大学院・医学研究科)
森琢磨(京都大学・霊長類研究所)
根東覚(東京医科歯科大学大学院・医歯学総合研究科)
大脳皮質のGABA作働性介在ニューロンには多数のサブタイプがあり,各サブタイプの機能的解析は,皮質回路網の神 経結合解析やその形成を理解するのに不可欠である。しかし形態的・生理的多様性にも関わらず,その数は錐体細胞と比較して少なく,同定は容易ではない。介 在ニューロンの同定を容易するためには,抑制性回路機能を正常に保ちつつ,GABAニューロンや,そのサブタイプの細胞体・樹状突起が蛍光観察できるラッ トやマウスが利用できることが望まれる。大脳皮質GABAニューロンの主要なサブタイプの一つにペプチドのソマトスタチンを発現する細胞がある。ソマトス タチン遺伝子にIRESシグナルを付けてGFPとIL-2Rαの融合遺伝子を挿入したマウスを作製し,その大脳皮質での発現を調べた。また,GABA ニューロンが蛍光識別できる遺伝子改変ラット作成の準備を行った。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
関係論文
小林康(大阪大学大学院生命機能研究科)
渡邊雅之,伊佐正
眼前のいくつかの標的に対してヒトやサルは衝動性眼球運動(サッカード)とよばれる非常に速く,最適化された弾道的 な眼球運動で視野を移動させる。サッカード制御には中脳の上丘や大脳皮質が重要な役割を果たしていることが明らかになってきた。サッカード運動の実行には 上丘におけるバースト活動の寄与が大きいと考えられているが,サッカード中の上丘におけるバースト活動は上丘中間層の運動マップに相当した特定のニューロ ン群で最初に生じ,次にそのニューロン活動はサッカード運動のダイナミクスによく似た時間経過で発火の増減が起きることが知られている。さらに,上丘の活 動領域は時間とともにサッカード実行に関係する尾側のサッカード領域から吻側の固視領域へと移動していくことが知られている。この上丘内でのサッカード領 域から固視領域にかけての興奮伝播の空間的な制御,発火頻度の時間パターンの調節が弾道的なサッカード運動の制御に必須であるとする仮説と,それを否定す る仮説があり,未だに完全に決着がついていない。
本研究ではこのような神経回路内でのニューロン活動の時空間的な伝搬がサッカードという弾道運動制御のダイナミクス を作り出しているか否かということに対して答えを出していきたい。そこで,サルの上丘にアセチルコリンのアゴニストであるニコチンを微量注入し,上丘局所 回路のニューロン活動の時空間パターンに擾乱を与えた時にサッカードがどのような影響を受けるか検討した。
上丘へのニコチンの微量注入後,注入部位の神経細胞群が表現する領域(注入部位表現領域)に向かう自発サッケードが 頻発した。この結果は,ニコチンが上丘神経細胞活動を亢進させるという仮説と一致する。また,視覚誘導性サッカードにおいてサッカードの標的が上丘の注入 部位表現領域近傍に呈示された場合,サッカードの反応潜時が短縮した。この結果もニコチンにより上丘の局所活動が亢進したことによると思われる。一方, サッカードの標的が注入部位表現領域から離れていた場合には上丘内の抑制性内在性回路による運動準備期間中の活動の抑制に起因する反応潜時の遅延が予想さ れる。ところが,予想に反してニコチン注入後,反応潜時には変化が生じなかった。この結果より上丘内の抑制性内在性回路が運動制御に及ぼす影響がそれほど 強くないということが示唆された。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
発表論文
福井 豊, 岩山 広(帯広畜産大学・畜産学部・家畜増殖学研究室)
保地 眞一(信州大学・繊維学部・資源生物学講座)
平林 真澄, 加藤 めぐみ(生理学研究所・脳機能分子解析室)
海棲哺乳類であるヒゲクジラ類(ミンククジラなど)の体外受精,特に顕微授精による受精卵作出の報告はない。本研究 では,ガラス化されたクロミンククジラ卵子を加温後に体外成熟させ,成熟卵子へ同種の凍結融解精子を用いて卵細胞質内精子注入(ICSI)を行い,その後 の体外培養により胚盤胞への発生能を検討することを目的とした。
平成16年度では,Cryotop およびOPS (Open pulled Straw) を用いてGV期のクロミンククジラ卵子のガラス化保存を試みるとともに,体外成熟培地に浸透圧を390 mOsMにまで高めた修正TCM199を用いて加温後の卵子成熟率について検討した。卵子は,第16次(2003/2004年)南極海鯨類捕獲調査で捕獲 されたクロミンククジラ(成熟雌:56頭,未成熟:32頭)から直径2~15 mmの卵胞を吸引採取した。ガラス化保存は,CryotopおよびOPSに凍結保護物質に15%エチレングリコール+15%ジメチルスルホキシドを用い た。加温後の卵子はガラス化保存容器(Cryotop,OPS)およびクジラの成熟度(成熟,未成熟)の計4実験区において,40~50時間の体外成熟培 養後の成熟率を比較検討した。
加温後の卵子形態正常率は,Cryotop区(成熟:83.4%,未成熟:80.8%)がOPS区(成 熟:67.7%,未成熟:64.2%)に比べて有意に高かった(P<0.05)。ガラス化保存容器による体外成熟率は,Cryotop/成熟クジラ区 (29.3%)が他の実験区(10.1~13.2%)よりも有意に高かった(P<0.05)。
体外成熟培養時間については,50時間よりも40時間でICSIできる良好な正常卵子が得られた。しかし,その後の体外培養で2~4細胞期の胚が得られたが,それ以降の胚発生は休止した。今後,さらにクロミンククジラ卵子のガラス化保存法の改良とともに,1) 卵子成熟培養時間の確定,2) ICSIにおける卵子活性化処理の有無とその方法,3) 体外培養系の改善を検討する予定である。
保地 眞一,岩浪 亮人(信州大学・繊維学部)
平林 真澄,加藤 めぐみ(自然科学研究機構・生理学研究所)
ラットは脳機能解析のモデルとして欠かせないが,胚性幹細胞が樹立されていないことや安定したクローン個体の作製技 術が未開発なことから,特定の遺伝子機能を封じ込めたノックアウトラットを作製する手立てはない。本研究では,ラットから未分化の精原細胞を体外で培養 し,円形精子細胞に分化させてから顕微授精してラット産仔を得ることを試みた。ラット円形精子細胞の顕微授精による産仔作製には,本共同研究に先立ってす でに成功しており(Mol Reprod Dev 2004, 69, 153-158; Contemp Top Lab Anim Sci 2004, 43/2, 13-15),体外での精子細胞への分化誘導技術を確立し,当該幹細胞を株化できれば,遺伝子組み換えした生殖幹細胞由来のラット個体を作製する道が開け る。
出生後7.5日目の雄ラット(精母細胞も精子細胞も未出現)の精巣から,コラゲナーゼとトリプシンを用いて Type-A精原細胞を採取した。この精原細胞を同時に単離したセルトリ細胞のフィーダー上でドーム状にして10日間培養(前半3日間は37℃,後半7日 間は34℃)した。EGFPを発現するトランスジェニックラット(ヘテロ)のG1産仔を用いた場合,培養10日目に53.5%がEGFPの蛍光を発する形 態的にも円形精子細胞様の細胞集団が得られた。培養過程における細胞の倍数性分布をフローサイトメトリーによって調べたところ,培養6日目から1cのピー クが出現していたことがわかった。そこで排卵ラット卵子658個にこれらの細胞核を顕微注入し,直流パルスと6-DMAPの併用による人為的活性化処理を 施した。計375個の顕微授精卵をレシピエントに移植したが,27個の着床痕が認められたのみで生存産仔は得られてこなかった。培養前後の細胞集団を RT-PCRで比較することにより,半数体細胞特異マーカー遺伝子のProtamine-2が培養後の円形精子細胞様の細胞で発現していることを確認し た。しかし,同じく半数体細胞特異マーカーであるTP1/TP2は発現していなかった。なお,ここまでの実験結果は大学院生を筆頭著者とした論文として Theriogenology誌に投稿し,2005年5月13日付けで正式受理されている。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
関係論文
島田 昌之(広島大学大学院・生物圏科学研究科)
伊藤 潤哉,加藤 めぐみ,平林 真澄(自然科学研究機構・生理学研究所)
本研究では,クローンラット作製方法の確立およびその効率改善を目的として,ラットにおいてクローン作製を困難にし ている原因の一つであるラット卵子の活性化機構について検討した。はじめに,他の動物種で核移植した胚において誘起される早期染色体凝集(PCC)が, ラット再構築胚で認められない原因について追究した。その結果,ラット排卵卵子を体外で培養すると,自発的に第二減数分裂を再開し,それに伴って早期に低 下した成熟促進因子(p34cdc2 kinase)により,PCCの形成が起こらないこと,また除核した卵子ではさらにp34cdc2 kinase活性が低下することを明らかにした。一方,プロテアソーム阻害剤で処理した核移植胚ではp34cdc2 kinase活性の低下は緩和され,PCC誘起率は改善された。これらの結果により,p34cdc2 kinase活性とPCCの形成との密接な関係が明らかにされた。次に,ラットの系統間におけるp34cdc2 kinase活性の違いとその原因について検討したところ,Wistar系統では著しいp34cdc2 kinase活性の低下とMos/MEK/MAPKの早期の不活性化が認められたが,Sprague-Dawley(SD)系統ではほとんど認められなかった。また,プロテアソーム阻害剤で処理したWistar卵子では,Mosおよびcyclin B(p34cdc2 kinaseの制御部位)の低下も抑制された。さらにSD卵子をMEK抑制剤U0126で処理すると,p34cdc2 kinase,MEK/MAPKの両方の不活性化が起こり,多くの卵子が前核を形成した。以上のことから,ラットではMosおよびp34cdc2 kinase活性が細胞周期停止因子(CSF)として機能していること,またCSFの活性は系統によって大きく異なることが初めて明らかされた,さらに除 核によってCSF活性が減少する原因について検討したところ,除核直後では活性は低下しておらず,その後短時間のうちにMos,cyclin Bの減少による不活性化が起こることが明らかにされた。一方脱リン酸化抑制剤,プロテアソーム阻害剤の複合処理を行うことにより,除核卵においてもCSF 活性を高く維持することに成功し,これらの再構築胚のほとんどでPCCが誘起された。今後これらの知見はクローンラットの作製に十分に応用できると考えら れる。
安居院高志 (北海道大学大学院獣医学研究科)
尾崎 毅 (自然科学研究機構・動物実験センター)
aganglionosis rat (AR) は被毛色の欠損と腸管神経節欠損のため巨大小腸・結腸症を呈するヒトHirschsprung病のモデル動物である。原因遺伝子はエンドセリンレセプタータイプB (Ednrb)遺伝子の部分欠失であることが既に我々を含めた複数のグループにより明らかにされている。ARは巨大小腸・結腸 症のために生後3週齢で全例死亡するが,我々のこれまでの研究から,他の系統ラット(LE)と遺伝背景が適度に混じりあうことで被毛色の欠損は起こるが, 巨大小腸・結腸症が軽度となり3週齢で死亡することなくadultまで成長するラットが出現するという事実が発見された。この原因となっている遺伝背景の 本体を明らかにすべく,LE-+/EdnrbslとAR-+/Ednrbslとを交配して得られるF2(LE.AR)- Ednrbsl /Ednrbslを2週齢でsacrificeし,腸管神経節欠損の程度を数値化するとともに全ゲノムスキャンを行い,これらのパラメーターを用いてquantitative loci (QTL)解析を行うことを計画した。交配により解析に必要な個体を得るのは効率が低いために大変時間が掛かるが,現在までに約100匹のEdnrbslホ モ個体を得,それらの腸管神経節欠損の程度を測定し,同時に尾からゲノムDNAを調製した。当初はF2における腸管神経節欠損の程度は複数の遺伝子座に支 配されているであろうから連続的な値を取ることを予想していたが,これまでにサンプリングしたF2の腸管神経節欠損の割合のデータから,重症度のものと軽 症度のものとに3:1の比に分離していることが判明した。このことは腸管神経節欠損をレスキューしている遺伝子は1つないしは2つであることを示唆してい る。今後はマイクロサテライトマーカーとの連鎖解析によりこれらの遺伝子座を同定し,更には遺伝子の同定へと進んでいく予定である。
筒井泉雄(一橋大学)
井上 勲(一橋大学)
尾崎 毅(動物実験センター)
無脊椎動物の中でも極めて複雑な行動様式と学習能力を有する軟体動物の脳の情報処理システムの解明を目的として実験 を行った。軟体動物の行動は主脳、視神経節、星状神経節の統合作用で行われている。イカは危険を感知すると高速度で危険からの逃避行動を起こし,また獲物 を見つけるとすばやく食腕を放出する。イカは普段の遊泳時には決して培養水槽の壁に激突することがないが,驚かせると非常に早い逃避行動を行い水槽の壁に しばしば激突する。ここには制御を伴った行動と急速な制御不能の行動が存在している。また食腕は高速度で獲物に向かって放出され高確率で獲物を捕獲する。 食腕の吸盤が密生している先端部分は獲物に接触するや否や獲物を包み込むような複雑な行動を始める。餌の完全な捕獲後,餌は口器のところまで急速に食腕に よって引き戻される。捕食行動はこのように捕獲のための早い行動と,正確な補足のための行動の二重支配によって制御されている。このようにイカは早い筋収 縮を伴う行動と比較的緩やかな制御可能な行動の二種類の運動支配系を保持している。この行動制御がどのような神経系によって支配されているのかを今回解明 した。
食碗は主として中央長軸沿いの縦走筋と周辺部にある輪走筋から成り立っている。輪走筋の収縮によって食碗の放出,縦 走筋の収縮によって食碗の回収が行われている。食腕の吸盤が存在する先端部分と中央部を切り出し切片を作り,食碗先端部と中央部の縦走筋と輪走筋に対する 神経伝達物質の作用機序を解明した。結果,先端部(吸盤集結部)をのぞいた輪走筋ではアセチルコリンよって単独の興奮性支配が行われているが,先端部では アセチルコリンによる興奮性支配と,グルタミン酸による抑制性支配の二重支配が行われていることが判明した。さらに,逃避行動の主要因であるジェット噴射 を行うマントルの輪走筋と縦走筋についても切り出し同様の実験をおこなった。結果,食腕と同様に輪走筋ではアセチルコリンよって単独の興奮性支配が行われ ているが,縦走筋ではアセチルコリンによる興奮性支配と,グルタミン酸による抑制性支配の二重支配が行われていることが判明した。
獲物を捕らえる蝕腕の投射や,急速な逃避行動は興奮性の筋肉制御のみが関与し,最大限の速度を出すように制御が行わ れ,微調整が必要な行動に対してのみ抑制性の神経支配が関与することが今回明らかになった。さらに,抑制性は脳を通じて支配されているが,アセチルコリン を介する早い制御系は星状神経節を介して発火している事も判明した。今後さらにイカを含む軟体動物における脳,神経節間における二重制御を可能とする微細 運動機構,分散情報処理機構の解明を目指すものである。
臼田信光,谷口孝喜,中沢綾美,厚沢季美江(藤田保健衛生大学・医学部)
金子康子,仲本準,新田浩二(埼玉大学・理学部)
中山耕造,亀谷清和,橋本 隆(信州大学・医学部)
前島一博(理化学研究所)
登阪雅聡(京都大学・化学研究所)
永山國昭(岡崎統合バイオ)
前年度に引き続き高コントラストを特徴とする電子位相顕微鏡法のうち微分干渉法(ヒルバート微分法)とゼルニケ位相 差法を用いて種々のテストを行った。高加速の300kV電顕を用いた位相差法では,氷包埋を行った脊椎動物の細胞を材料として電子染色なしで高コントラス トの電顕像が得られた。培養全載細胞観察においてはミトコンドリア等の細胞小器官と微小管等の細胞骨格が明確に認められた。血小板や精子においては細胞内 部構造が立体的に観察された。同様の観察はウィルス・バクテリアにも適用可能であった (Kaneko Y et al., J Electron Microscop 54, 79-84, 2005)。本法の生物系への応用への可能性が強く示唆された。また,観察される構造を組織化学的に標識して,光学顕微鏡と電子位相顕微鏡と同一細胞を観 察する試みている。さらに,位相観察法を高分子材料にも適用した。電子染色法の適用が困難なゴムの観察に適用して,十分なコントラストの有る像が観察さ れ,位相差電顕が,生物材料に加え高分子材料にも適用できることがわかった(化学工業日報,日経産業新聞)。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
発表論文
加藤幹男(大阪府立大・総合科学)
永山國昭,片岡正典,Radostin Danev(岡崎統合バイオ)
本研究では,生物ゲノムに存在する特徴的な塩基配列の,染色体構築と遺伝子機能制御における生理意義の解明を目的と して,まずサテライト,ミニサテライトに代表される縦列型反復DNA配列に注目し,その高次構造特性の解析を進めている。ミニサテライトDNA領域は,そ の縦列回数はきわめて多型性に富んでおり,その原因として不等交叉や複製時の伸長/欠失が想定されている。今回,海水魚Acanthopagrus latus由来の30bpを単位鎖長とするミニサテライト配列が,in vitro相補鎖合成(PCR反応)において,伸長/欠失を起こすことを見出したので,その原因となる構造因子を求めるために,電気 泳動移動度解析,化学修飾解析,円偏光二色性スペクトル解析,示差走査熱量測定等の生化学的解析に加えて,高分解能電子顕微鏡解析を試みた。その結果,相 補鎖合成の鋳型となる一本鎖DNAは,反復単位鎖長においてヘアピン様構造(ステム-ループ構造)を形成し,さらに,マグネシウムイオンの存在下では,塩 基対形成を変化させることなく強く凝縮した構造を形成することがわかった。このような一本鎖DNAの高次構造形成が,新生鎖と鋳型鎖のミスアライメントを 誘発し,繰り返し数の変異をもたらすものと考えられる。今後,それぞれの相補鎖間において形成される微細構造の差異を,さらに高解像度の電子顕微鏡像を得 ることによって明らかにするとともに,DNAの凝縮や弛緩を制御する要因をとらえたい。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
発表論文
恵良聖一,根川常夫(岐阜大学大学院医学系研究科 分子生理学分野)
林 知也,西川弘恭(明治鍼灸大学 生理学)
村上政隆(自然科学研究機構統合バイオサイエンスセンター ナノ形態生理学)
血液中に多量に存在する血清アルブミン分子には反応性の高いSH基が1個存在し,このSH基がフリーの状態のアルブ ミンを還元型アルブミン,一方このSH基が酸化された状態のアルブミンを酸化型アルブミンと呼び,通常は両者が混在している。単離したラット顎下腺を用い たこれまでの研究で,血液中のアルブミンが傍細胞経路を通って唾液中にわずかながら漏出されることが明らかになり,さらにその際タンパク質の翻訳後修飾と して,一酸化窒素(NO)がSH基に結合したS-ニトロソアルブミンの存在が示唆された。今回はNO合成酵素阻害剤を用いて,これらのことの検証ならびに 発生するNOが唾液分泌に対していかなる影響を及ぼしているかを検討した。
10~11週齢の雄性ウィスターラットの顎下腺を麻酔下で単離し,市販のヒト血清アルブミン(HAS)を含むKrebs-HEPES緩衝液(pH 7.4, 37℃, 100% O2)にて灌流した。カルバコールにて唾液分泌刺激を行い,静脈液,組織間液,唾液を採取し,それぞれの溶液中のHSAの酸化・還元状態ならびにS-ニトロソアルブミン量を特殊なカラムを装着したHPLCによって分析した。NO合成酵素阻害剤としてl-NAMEを用いた。
まずカルバコール刺激に加えてl-NAME存在下と非存在下での唾液分泌量(μl/min)を調べたが,l- NAMEは唾液の分泌量に対してほとんど影響を与えなかった。またl-NAME非存在下ではS-ニトロソアルブミンの修飾が16.2±11.6%,不可逆 的な酸化型アルブミンのそれが14.8±9.7%程度観測されたが,l-NAME存在下ではいずれのタイプの修飾アルブミンもほとんど検出されなかった。 Secretion/Perfusate (S/P) 比 (%) はl-NAME非存在下では0.17±0.10%,存在下では0.52±0.80%となり,値のばらつきが大きくなった。
これらの結果から,HSAがラット顎下腺組織のタイトジャンクションのような傍細胞経路を通過するときにアルブミン は明らかにNOによってニトロソ化修飾を受けていることが確認された。さらに,パイロットスタディとして行った,タイトジャンクションの開口を促進すると されるイソプロテレノールを用いたスタディによっても,アルブミン分子が傍細胞経路を通過して唾液中に漏出されていることが検証された。
村上政隆(統合バイオ生理研)
橋本貞充,松木美和子(東京歯大)杉谷博士,勝俣 治(日大松戸歯)
Alessandro Riva, Felice Loffredo, Francesco Loy (University of Cagliari)
従来,単離腺細胞において分泌刺激に遅く反応するものと素早く開口分泌反応するものが共焦点レーザー顕微鏡により観 察されていたが,前者は多くの場合,低機能あるいは病的と認識され棄却されてきた。しかし摘出灌流標本の電子顕微鏡観察においても一斉に分泌反応を起こす のではないこと,静止時の電子顕微鏡観察でも開口分泌反応がごく一部にあることなどから微視的素分泌と巨視的分泌が異なる時間経過を持つ可能性があがっ た。本研究の目的は,1) 新たに神経支配つき摘出灌流標本の開発,共焦点レーザー顕微鏡下で色素希釈,開口分泌を観察し,2) 生理的至適濃度の探索し,新たに生理的範囲の巨視的水分泌および蛋白分泌の時間経過を測定する。この実験を通じ3) 電子顕微鏡レベルの微細構造変化を観察し,巨視的機能の連係をはかる。
岡山大学よりラット顎下腺の神経分離法を導入,生理研の単離標本作成技術とあわせ,神経支配つき摘出灌流標本の作成 を試行した。しかし,副交感神経である節前繊維は導管周囲の結合組織内に散在するため,導管自身を電気刺激する計画に変更した。さらに電気刺激による分泌 反応のばらつきが大きく,さらに試行を繰り返す必要がある。摘出灌流標本のConfocal Laser Microscopeへの設置を日大松戸歯学部で行うための第一段階として還流実験系の立ち上げを行った。電子顕微鏡標本で得られた微視的反応のデータを 空間的な確率変化と捉える試みとしてカリアリ大学でラット顎下腺の高分解SEM標本から分泌細管表面面積あたりのmicrovilli pit数およびmicrobud数を計数を開始した。開口分泌が活性化し,蛋白分泌が増加する場合にはmicrovilliの消失が観察される。また microbudは開口分泌後の細胞膜のendocytosisによる回収を定量化するものと想定される。しかしこれらの分布は均一ではなく全体像として 観測計測しなければならない。幸いmaceration法により細胞間分泌細管全体を細胞質側よりSEM観察ができるため,透過電子顕微鏡像のような超薄 切片観察に比べ,定量的に評価が可能である。カリアリ大学ではヒト唾液腺スライスで刺激薬品を変えた実験を実施し,刺激の種類によりmicrovilli pit数およびmicrobud数が変化することを定量した。継続して,ラット耳下腺および顎下腺の分泌蛋白とこれらの計数の比較を進めている。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
発表論文
大塚 幸雄(産業技術総合研究所)
亀山 仁彦(産業技術総合研究所)
岡本 治正(産業技術総合研究所)
岡戸 晴生(東京都医学研究機構)
海老原 達彦(産業技術総合研究所)
岡村 康司
前年度までに同定したマボヤCaチャネルのβサブユニットの役割を個体レベルで解明するため,βサブユニットのアンチセンスDNAを受精卵に微小注入し,発生および運動機能に及ぼす影響を検討した。
まず,Caチャネルの発現にどのような変化が生じるかを,B5.1割球(筋細胞)の電位固定法による計測により検討したところ,βサブユニットのアンチセンスDNAを導入した細胞ではほとんどCa電流が記録されなかった。
同じ条件でアンチセンスDNAを導入した胚について形態を観察したところ,嚢胚に以上が見られたもの,尾部の伸張が 見られないもの,形態的には正常だが運動機能を示さないもの,の3群に分類できた。これらのフェノタイプの重症度は注入したDNAの濃度に依存していた。 また同様なフェノタイプはαサブユニットのアンチセンスDNAを導入した胚についても観察された。いくつかのコントロール実験の結果,発生途中のCaチャ ネル機能が形態形成に重要であることが示唆された。
更に,形態が正常であるが運動機能を示さない群についてそのメカニズムを明らかにするためファロイジン染色を行っ た。CaチャネルのアンチセンスDNAを導入した胚で形態が正常なオタマジャクシ幼生では,尾部骨格筋の筋線維の走行がランダムになっており,また細胞膜 表層部の分布が著明に減少していた。細胞同士のジャンクション領域のアクチン線維も減少していた。δ-ツボクラリン投与,アクチンミオシン相互作用の阻害 剤でも同様な効果が見られたことから,発達期の神経活動に依存した筋細胞膜の電気的興奮性を介したCaチャネルからのCa流入が,筋細胞のアクチンフィラ メントの走行の構築には重要であることが示唆された。
森 泰生(京都大学大学院工学研究科)
原 雄二(京都大学大学院工学科)
清中 茂樹(京都大学大学院工学科)
片野 正展(京都大学工学研究科)
山本 伸一郎(京都大学工学研究科)
西野 敦雄,岡村 康司
ユウレイボヤゲノムからTRP関連遺伝子を網羅的にリストアップする作業を行い,TRPMが2個,TRPCが8個,TRPV/N/Aが8個,TRPPが9個,合計27個の遺伝子が存在すると考えられた。そのうちほとんどは対応するESTの情報が存在していた。
特筆すべき点として,TRPMのグループを除いてホヤ独自の枝を形成する遺伝子の多様性が見られたことである。このことはホヤの独自の生理機能に特化する形でTRP関連遺伝子の多様化が生じたことを強く示唆する。
また,TRPVファミリーとしては,脊椎動物の遺伝子よりも線虫のものに近い二つの遺伝子が存在していた。 TRPV/N/Aについてはゼブラフィッシュで機械受容チャネルとして同定された分子であるNOMPCのホモログ遺伝子がひとつ存在し,アンキリンリピー トを有するTRPA(最近哺乳類の聴覚受容細胞での機械受容チャネルと報告された)と相同な遺伝子が4つも存在していた。現在これらのTRP関連分子の cDNAクローニング,及び機能の同定や発現パターンの解析に関する実験が進行中である。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
発表論文
岡村 康司,高木 正浩
白幡 恵美(山形大学小児科)
早坂 清(山形大学小児科)
木島 和己(山形大学小児科)
吉田 繁(近畿大学)
川畑 篤史(近畿大学)
関口 冨美子(近畿大学)
前年に見いだしたアンキリンGによるナトリウムチャネルの持続性電流の抑制のメカニズムを更に詳細に明らかにする実 験を行った。神経系に発現するもう一つのアンキリンアイソフォームであるアンキリンBをNav1.6とともにtsA201細胞に発現させたところ,持続性 電流の減少は起こらなかった。二つのアンキリンによる効果の違いがアンキリン分子のどの分子内領域の構造の違いに依存するのかを明らかにするため,更にア ンキリンBとアンキリンGとのキメラ分子を用いてホールセルパッチクランプによる記録を行った。その結果,N末端側の膜結合ドメインがアンキリンG由来で あるときに限定して持続性電流の抑制が見られ,持続性電流の制御には膜結合ドメインを介してNav1.6タンパクと結合することが必要であることが示唆さ れた。
【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)
発表論文
関係論文